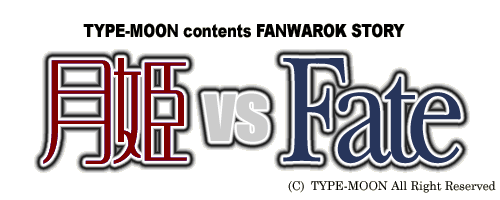
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[11]
-
6
「【矛盾】しているゆえ……か」
濃霧に包まれた樹海に再び黒髪の青年が姿を現していた。
彼の右方向には元の姿に戻ったアルクェイドが倒れている。左方向には黄金色に輝くドーム――赤毛の魔術師と騎士の英霊が中にいるであろう宝具の結界――が見えた。いずれも全力を出し切り、ついには限界を越え、こうした状態になったらしい。
(無茶なことを)
青年は倒れているアルクェイドを懐かしそうに眺めた。
いかに《世界》の修正力が弱かろうと《白き姫》は限りなく《朱き月》に近い存在だ。おそらく無意識的なことだろうが、彼女は自らを本物の“千年城 () ”に封じ込めている《白き姫》――いや、《朱き月》の器と言うべきか?――に近づけることで《朱き月》の侵食を防いだつもりでいたらしい。だが、それは断崖絶壁のスレスレのところまで踏み出したも同然の行為だ。
いや、普段の“吸血衝動を抑えつつ力を出す感覚”が災いしたのかもしれない。
二年前には七割の力で抑えられた吸血衝動も、今では九割の力を費やさなければ抑えきれないまで強まっている。つまり彼女は平素から限界ギリギリの状態にいることを余儀なくされるようになったのだ。
同じ感覚で《朱き月》を抑えつつ《白き姫》であり続けようとしてしまった。
無茶なことだ。
もっとも、反動を気絶という遮断行為で防いだあたり、それなりに考えていたのかもしれない。
「さて……」
青年は濃霧の彼方を見据えた。
「挨拶ぐらいさせてもらえないか、我が娘よ」
瞬間、何かが濃霧を切り裂き、青年へと飛び抜けてきた。
黒鍵だ。それもひとつやふたつではない、数十本という黒鍵が、恐るべき猛速度で濃霧を突き破り、青年のもとに迫ったのだ。
だが、全ての黒鍵が青年の躰をすり抜けていった。
後方の樹木に黒鍵が突き刺さる。火葬式典による猛烈な衝撃と熱が、一瞬にして数本の大木を燃やしながら砕いていった。
直後、さらなる殺意の塊が真っ向から青年に向かって肉薄してきた。
シエルだ。
赤い瞳を殺意に塗り固めた埋葬機関の第七位は、普段着のまま、左右の手に黒鍵を握りしめつつ、一気に黒髪の青年を切り裂こうと肉薄したのだ。
しかし、その刃も青年の躰をすり抜ける。
「落ち着きたまえ、エレイシア」
「その名を――!」
彼女はさらに黒鍵で斬りつけた。
もちろん、いずれも彼の躰をすり抜けてしまう。黒鍵は護符としては優秀だが、その刀身に刻まれる火葬式典は受肉した相手にのみ効果を発揮する。そのことをわかっているはずだが、シエルは狂ったように青年を切り刻もうとしていた。
「……そうか」
青年の姿がかき消えた。
「私は本物の“アカシャの蛇”ではない」
再び背後から声が響く。シエルは振り返りつつも、ギョッとしたまま動けなくなった。
「確かに私は“アカシャの蛇”と呼ばれた存在概念を核とし、何代目かの“アカシャの蛇”の外見を獲得した状態で、不完全ながらこの世界に留まっている存在だ。しかし、“アカシャの蛇”という現象はすでに消滅している。ここにいるのは、その残滓だ。おそらく世界が限界を迎えるより前に、私が“私”と認識している存在も消えるだろう」
「……嘘です」
「その証拠に、今の私には反転衝動が存在しない」
「嘘です」
「いや、君はわかっているはずだ」
「……そうですね」
シエルは黒鍵を地に突き立てた。
「あなたは霊体として留まっているだけ……いずれ消え去る不完全な存在です」
「正確には霧を媒体に結びついている状態だよ」
「言われなくてもわかっています」
シエルは不機嫌そうに彼を睨み返した。
“アカシャの蛇”ミハイル・ロア・バルダムヨォン――シエルの人生を狂わせた張本人が目の前にいる。これを憎まずに誰を憎めというのか。
「それで、わざわざ姿を現した理由はなんですか?」
「ひとつは――」
ロアは優しげに目を細めた。
「君とゆっくり話してみたかった」
「お断りします」
「君にした数々の行いを反省するつもりも、謝罪するつもりもない。私は自らの求めるままに運命に挑戦してみただけだ。だから君が私を怨むことにも何も言うつもりはない。ただ、同じ根源を宿す者――それも限りなく根源に近いところにいる者として、私が君に好感を抱くのは自然なことだ。そうは思わないかね?」
「望んでそうなったわけではありません」
「そう、運命とは過酷なものだ。誰も望んだ人生を歩むことなどできない」
「話はそれだけですか?」
「それでも運命に逆らいたいと思う者がいる。それはなぜだ?」
「………………」
「運命に逆らう――それは意志だ。だが、意志とは何か。ちょうど私が君だった頃、様々な文献を読んだことを覚えているかね? プロシアのオカルティストの文献は?」
「忘れました」
「ルドルフ・シュタイナーは人智学という学問を立ち上げ、その中で人の魂や世界の有り様について面白い考察を行っていた。世界はアーリマン的なものとルシファー的なもののバランスと循環で成り立っているという説だ」
「……それが?」
「彼の考察によれば、人は最初に情動、感情というルシファー的なものを獲得した。しかしその後、知性、理性というアーリマン的なものを獲得した。時の流れと共に人と社会はアーリマン的になっていき、最終的に変化や流動性が微塵もない、氷のような状態になると彼は予見した。当時の氷宇宙論の流れを組む思想だ」
「それと今回の異変が関係していると言うのですか?」
「いや、直接的には関係していない。だが、無関係というわけでもない」
ロアは右手を振った。
濃霧が動き、霧の無い晴れ渡ったトンネル状の空間が出現した。
「《白き姫》を背負いなさい。この森の出口まで案内しよう」
シエルは黙り込んだがロアの指示に従うことにした。もちろん、不承不承といったところだったが。
「エレイシア。神秘とは何か、考えたことがあるかね」
「その呼び方はやめてください」
気絶したアルクェイドを背負ったシエルは、ロアと並んで歩きながら不快そうに眉をひそめていた。
「では、シエルと呼ぼう」
ロアは気にする様子もなく言葉を続けた。
「神秘とは【矛盾】だ。極論するなら、この宇宙に神秘が存在する余地など無い。もし、神秘が存在すると言うなら、それは観察者の知性の中だけのこと。物理的な事象は、すべからく物理的に完結している。つまりもともと、この世に神秘など存在するはずがないのだよ」
「神学論争に興味はありません」
「うむ、確かにそれでも神秘は実在している。私がそうだし、君もそうだ。《白き姫》も、《朱き姫》も、あの赤毛の魔術師や“死の少年”も――この世には神秘の具体的な証明がある。これは大きな【矛盾】だ」
「【矛盾】……」
アルクェイドはこう告げていた。
――因果律が崩れたのよ。並行世界全てを見渡しても、存在してはいけない出来事が起きてしまった……だから《世界》が、それを修復しようとした。それに巻き込まれたってこと。
つまり大きな【矛盾】の発生が、今回の異変の原因だということになる。
そしてロアは、神秘そのものが【矛盾】だと告げている。
「霊など存在しない」
ロアはさらに告げた。
「魔術も、魔法も、幻想種も、超越種も、超能力も、異能者も、なにひとつ、本来は存在してはいけないものだ。しかし、この世界には存在している」
「《世界》が許容できる【矛盾】だから……」
「いや、そもそも【矛盾】に“許容”などという概念は当てはめられない。それは“色”を“走る”と表現するのと同じレベルの考え方だ」
「でも神秘は実在しています」
「そう、実在している。だが、いつから実在が許されたのか」
ロアは立ち止まった。
「エレイシア、君は並行世界についてどう考える?」
「考えたこともありません」
同様に立ち止まったシエルが言い返した。ただ、“エレイシア”と呼ばれていることも気にせず、まるで講義を受ける教え子のような振る舞いになりはじめていることにも気づいていない。
短い間とはいえ、同種の存在となった経験がそうさせているのだろう。
いや、複数の世界線の記憶が混在するせいで、微妙に頭の中が混乱しているからこそなのかもしれない。
いずれにせよ、ロアとシエルは、一介の教師と生徒のように語り合い続けた。
「並行世界の存在は確認されている。あの宝石の翁が、確認できるように“した”と言っても良いかもしれない。もっとも、あの男が定義づけた並行世界は、一般に思われているような“よく似た異なる世界が別に存在する”というものではないがね」
「確率的にしか……」
「そう、並行世界とは、あくまで観測者が現れたことで観念論的領域から唯物論的領域に浮上する仮想の概念にすぎない。つまり、並行世界とは空想具現化と同質の現象にすぎないということだ。もちろん、これは原則論としての見解であるため、何かと問題が残るのだがね」
「私が追体験した他の世界線の記憶については?」
「仮想のものと考えたければそれでも良いだろう。そもそも人の記憶など、蛋白質の配列にすぎない。こんなもので因果律が定まるなどという盲信、神秘の領域に住む者なら、笑い飛ばしておくのが健康的だろう」
「過去はひとつではない――と?」
「なぜひとつでなければならない?」
「【矛盾】するからです」
「そう、【矛盾】するからだ。しかし、この世には神秘という【矛盾】がすでに存在する。ならば、なぜ過去だけが【矛盾】してはいけない? 神秘の中には因果律そのものを改変してしまうものも少なくはないというのに」
「…………」
「エレイシア、難しく考えることはない」
ロアは優しく語りかけた。
「そもそも【矛盾】とは論理に反するという意味だ。論理とは知性。知性とは“ヒト”の魂が後天的に獲得してきた要素のひとつにすぎない」
「……因果律は?」
「存在する――と、我々の知性が判断している」
「《世界》は?」
「《世界》は観測者になりえない。《世界》はそこにあるだけだ」
「でも惑星霊がいます」
「“いる”と判断する知性が我々にあるからだ」
「……あなたは何を言いたいのですか?」
「色即是空、空即是色――ブッディズムの言葉だが、これこそ真理だということだよ」
「意味がわかりません」
「君にもいずれわかる時が来る。ただ、理屈や因果で全てを判断してはいけないということだけは覚えておくといい」
「――ロア、あなたは…………」
彼の姿が少しずつ薄らぎ始めていた。
限界が訪れたのだ。
シエルが知る神秘の“理屈”では、肉体を失った魂は長い時間、形を留めることができないことになっている。最初に肉体と魂の媒体となる精神体が崩れていき、次いで、魂も崩れていき……
――エレイシア。
ロアはシエルに微笑みかけた。
――違う道を歩めたのであれば、私は君の良い師になれたかもしれない。悔やまれることといえば、そのことだけだ。
「ロア……」
――気を付けたまえ、エレイシア。この世界は、過去に起こりえた“可能性”が、相互に【矛盾】したまま存在を許されている。不安定な“魔法”の連続使用……不完全な第二魔法で確率が歪められたところに、不完全な第三魔法が使用された。ありえない確率が“ある”ことにされてしまったのだ。神秘という【矛盾】を許した法則そのものが歪められたと言い変えてもいい。もちろん、原因のひとつはこの私だが、過去の様々な可能性の中で、生きることに執着した“意志”の幾つかが、この“【矛盾】世界”と呼ぶべき現象をつなぎ止めている。彼らを消せば、この異変を収めることができる。
「でも、だったら、あなたが消えるだけで――」
――私は執着などしていない。だから消えるのだよ。
彼は告げた。
――計らずとも君という後継者が得られた。永遠を求めた理由も、あの少年のおかげで理解できた。そして、そんな他愛の無い、笑える動機は、この胸にしまい込んだまま消えゆくべきだと……そう思えるようになった…………
ロアの躰は薄らぎ続ける。
――エレイシア。【矛盾】世界をつなぎ止める“意志”を消すんだ。もし君が知る者がいても、別物だと思え。それは無限の可能性の中で、もっとも生きることに執着した“意志”が、なんらかの力を得て顕現しただけの“現象”だ。私の時のようにためらうことなく戦うんだ。ただ……
彼は苦笑した。
――どんな時にも取り乱してはいけない。気を付けるんだ。いいね。
その言葉を最後にミハイル・ロア・バルダムヨォンは消え去った。
気配も消滅している。
だが、異なる遠い場所に別の“蛇”の気配があった。
「……なによ」
シエルはうつむいた。
怒りがこみあげてくる。
あれほど憎んだ相手が消えた瞬間、おもわず「待って」と言いそうになった。
そんな自分が無性に腹立たしい。
この怒り、どこにぶつけるべきか。
(…………………………あるじゃない、ぶつけるもの)
シエルは背負っていたアルクェイドを放り投げた。
――ドンッ!
「痛ったぁああああああ! なにすんのよぉ、このバカシエル!」
「寝たふりをして聞き耳たててる暴走超特急に言われる筋合いはありません」
「なによ! こっちが二回も心臓貫かれたのに助けにもこないし!」
「あんな怪獣大決戦に首を突っ込めと?」
「でもさぁ」
アルクェイドは服の埃を払いながら立ち上がった。
「なんか、懐かしいもの見ちゃった」
「なんのことですか?」
「さぁ?」
ニパッと笑った彼女は、両腕を後ろに回すとトコトコと歩き始めた。
「さーて、さっさと志貴と合流しなきゃ」
「……いいんですか、あの魔術師と英霊は」
「いいの、いいの。半分、成り行きで戦っただけだし。それに消さなきゃならない相手なら、志貴と合流したあとでも簡単に消せるじゃない♪」
「簡単にって……」
《朱き月》になりかけた《白き姫》と互角に争った相手を、それほど簡単に切り捨てて良いのだろうか。そういえば自分も、ロアにうながされたせいで、ついつい彼らを見逃してしまったが……
「おーい、バカシエルぅ! 置いてくよー!」
「あっ――待ちなさい、このアーパー吸血猫! 誰があんたをここまで担いで――」
「リン、現場に到着しました。すでに戦いは終わっています」
ライダーは宝石を介して凛に語りかけた。
――真祖と代行者は?
「移動中です。追跡しますか?」
――ううん、居場所がわかればそれでいいわ。で、衛宮くんとセイバーは?
「無事です」
ライダーは足下に視線を向けた。
そこには、大の字に倒れる士郎の姿があった。セイバーは、そんな彼の左腕を枕にするようにして横向きに倒れている。というより、ライダーの目には二人が樹海のただ中で昼寝でもしているかのように見えた。もちろん、少し離れたところにあった廃墟が、跡形もなく吹き飛んでいるのだから戦いがあったのは間違い無い。
――ライダー、先輩に怪我は?
桜の声が宝石から響いた。
「見たところ、怪我らしい怪我はしていません。セイバーも同様です」
安堵の吐息が聞こえてくる。
――ライダー。
今度は凛の声。
――悪いけど、ペガサス出して、連れ帰ってくれない?
「それでは敵側に見つかる可能性があります。よいのですか?」
――いいの、いいの。どういう理由か知らないけど、二人が無事ってことは真祖が見逃してくれたってことでしょ。だったら、真祖の気が変わる前に合流して対策練っておかないとまずいわ。それに聖剣が無い以上、真祖をどうにかできる方法、ライダーの宝具しか無いってことにもなるわ。その点でも、できるだけ早く合流しておきたいの。
「わかりました。では、すぐビルの方に」
――今、下にエレベーターで移動中だからビルの前に降りてきて。
「……電気が通じているのですか?」
――自家発電が稼働してるみたい。じゃあ、あとはよろしく。
「わかりました。桜のこと、よろしくお願いします」
通話はそこで途絶えた。
(さて……)
ライダーは改めて寝そべる二人に視線を向けた。
二人とも、実に幸せそうな寝顔だ。
「………………」
とりあえず――
「……うっ………………」
数分後、士郎が目覚めた。
「んっ……」
セイバーが小さくうめいた。見ると自分の左腕を枕にして、眠るように意識を失っている。
おそらく自分と一緒に気絶したのだろう。
ただ、こうしていると、二年前のあの頃に戻ったような――
(んっ?)
右腕にも重みを感じた。
ついでに右足に何か、温かくて柔らかいものが絡みついている気がする。
士郎は顔を右へと向けてみた。
なぜか邪眼殺しの眼鏡をかけたライダーの顔がすぐそこにあった。
「おはようございます、士郎」
「なんでさ」
こうして最初の激突は、《白き姫》の圧勝で幕を閉ざしたのだった。
濃霧に包まれた樹海に再び黒髪の青年が姿を現していた。
彼の右方向には元の姿に戻ったアルクェイドが倒れている。左方向には黄金色に輝くドーム――赤毛の魔術師と騎士の英霊が中にいるであろう宝具の結界――が見えた。いずれも全力を出し切り、ついには限界を越え、こうした状態になったらしい。
(無茶なことを)
青年は倒れているアルクェイドを懐かしそうに眺めた。
いかに《世界》の修正力が弱かろうと《白き姫》は限りなく《朱き月》に近い存在だ。おそらく無意識的なことだろうが、彼女は自らを本物の“
いや、普段の“吸血衝動を抑えつつ力を出す感覚”が災いしたのかもしれない。
二年前には七割の力で抑えられた吸血衝動も、今では九割の力を費やさなければ抑えきれないまで強まっている。つまり彼女は平素から限界ギリギリの状態にいることを余儀なくされるようになったのだ。
同じ感覚で《朱き月》を抑えつつ《白き姫》であり続けようとしてしまった。
無茶なことだ。
もっとも、反動を気絶という遮断行為で防いだあたり、それなりに考えていたのかもしれない。
「さて……」
青年は濃霧の彼方を見据えた。
「挨拶ぐらいさせてもらえないか、我が娘よ」
瞬間、何かが濃霧を切り裂き、青年へと飛び抜けてきた。
黒鍵だ。それもひとつやふたつではない、数十本という黒鍵が、恐るべき猛速度で濃霧を突き破り、青年のもとに迫ったのだ。
だが、全ての黒鍵が青年の躰をすり抜けていった。
後方の樹木に黒鍵が突き刺さる。火葬式典による猛烈な衝撃と熱が、一瞬にして数本の大木を燃やしながら砕いていった。
直後、さらなる殺意の塊が真っ向から青年に向かって肉薄してきた。
シエルだ。
赤い瞳を殺意に塗り固めた埋葬機関の第七位は、普段着のまま、左右の手に黒鍵を握りしめつつ、一気に黒髪の青年を切り裂こうと肉薄したのだ。
しかし、その刃も青年の躰をすり抜ける。
「落ち着きたまえ、エレイシア」
「その名を――!」
彼女はさらに黒鍵で斬りつけた。
もちろん、いずれも彼の躰をすり抜けてしまう。黒鍵は護符としては優秀だが、その刀身に刻まれる火葬式典は受肉した相手にのみ効果を発揮する。そのことをわかっているはずだが、シエルは狂ったように青年を切り刻もうとしていた。
「……そうか」
青年の姿がかき消えた。
「私は本物の“アカシャの蛇”ではない」
再び背後から声が響く。シエルは振り返りつつも、ギョッとしたまま動けなくなった。
「確かに私は“アカシャの蛇”と呼ばれた存在概念を核とし、何代目かの“アカシャの蛇”の外見を獲得した状態で、不完全ながらこの世界に留まっている存在だ。しかし、“アカシャの蛇”という現象はすでに消滅している。ここにいるのは、その残滓だ。おそらく世界が限界を迎えるより前に、私が“私”と認識している存在も消えるだろう」
「……嘘です」
「その証拠に、今の私には反転衝動が存在しない」
「嘘です」
「いや、君はわかっているはずだ」
「……そうですね」
シエルは黒鍵を地に突き立てた。
「あなたは霊体として留まっているだけ……いずれ消え去る不完全な存在です」
「正確には霧を媒体に結びついている状態だよ」
「言われなくてもわかっています」
シエルは不機嫌そうに彼を睨み返した。
“アカシャの蛇”ミハイル・ロア・バルダムヨォン――シエルの人生を狂わせた張本人が目の前にいる。これを憎まずに誰を憎めというのか。
「それで、わざわざ姿を現した理由はなんですか?」
「ひとつは――」
ロアは優しげに目を細めた。
「君とゆっくり話してみたかった」
「お断りします」
「君にした数々の行いを反省するつもりも、謝罪するつもりもない。私は自らの求めるままに運命に挑戦してみただけだ。だから君が私を怨むことにも何も言うつもりはない。ただ、同じ根源を宿す者――それも限りなく根源に近いところにいる者として、私が君に好感を抱くのは自然なことだ。そうは思わないかね?」
「望んでそうなったわけではありません」
「そう、運命とは過酷なものだ。誰も望んだ人生を歩むことなどできない」
「話はそれだけですか?」
「それでも運命に逆らいたいと思う者がいる。それはなぜだ?」
「………………」
「運命に逆らう――それは意志だ。だが、意志とは何か。ちょうど私が君だった頃、様々な文献を読んだことを覚えているかね? プロシアのオカルティストの文献は?」
「忘れました」
「ルドルフ・シュタイナーは人智学という学問を立ち上げ、その中で人の魂や世界の有り様について面白い考察を行っていた。世界はアーリマン的なものとルシファー的なもののバランスと循環で成り立っているという説だ」
「……それが?」
「彼の考察によれば、人は最初に情動、感情というルシファー的なものを獲得した。しかしその後、知性、理性というアーリマン的なものを獲得した。時の流れと共に人と社会はアーリマン的になっていき、最終的に変化や流動性が微塵もない、氷のような状態になると彼は予見した。当時の氷宇宙論の流れを組む思想だ」
「それと今回の異変が関係していると言うのですか?」
「いや、直接的には関係していない。だが、無関係というわけでもない」
ロアは右手を振った。
濃霧が動き、霧の無い晴れ渡ったトンネル状の空間が出現した。
「《白き姫》を背負いなさい。この森の出口まで案内しよう」
シエルは黙り込んだがロアの指示に従うことにした。もちろん、不承不承といったところだったが。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「エレイシア。神秘とは何か、考えたことがあるかね」
「その呼び方はやめてください」
気絶したアルクェイドを背負ったシエルは、ロアと並んで歩きながら不快そうに眉をひそめていた。
「では、シエルと呼ぼう」
ロアは気にする様子もなく言葉を続けた。
「神秘とは【矛盾】だ。極論するなら、この宇宙に神秘が存在する余地など無い。もし、神秘が存在すると言うなら、それは観察者の知性の中だけのこと。物理的な事象は、すべからく物理的に完結している。つまりもともと、この世に神秘など存在するはずがないのだよ」
「神学論争に興味はありません」
「うむ、確かにそれでも神秘は実在している。私がそうだし、君もそうだ。《白き姫》も、《朱き姫》も、あの赤毛の魔術師や“死の少年”も――この世には神秘の具体的な証明がある。これは大きな【矛盾】だ」
「【矛盾】……」
アルクェイドはこう告げていた。
――因果律が崩れたのよ。並行世界全てを見渡しても、存在してはいけない出来事が起きてしまった……だから《世界》が、それを修復しようとした。それに巻き込まれたってこと。
つまり大きな【矛盾】の発生が、今回の異変の原因だということになる。
そしてロアは、神秘そのものが【矛盾】だと告げている。
「霊など存在しない」
ロアはさらに告げた。
「魔術も、魔法も、幻想種も、超越種も、超能力も、異能者も、なにひとつ、本来は存在してはいけないものだ。しかし、この世界には存在している」
「《世界》が許容できる【矛盾】だから……」
「いや、そもそも【矛盾】に“許容”などという概念は当てはめられない。それは“色”を“走る”と表現するのと同じレベルの考え方だ」
「でも神秘は実在しています」
「そう、実在している。だが、いつから実在が許されたのか」
ロアは立ち止まった。
「エレイシア、君は並行世界についてどう考える?」
「考えたこともありません」
同様に立ち止まったシエルが言い返した。ただ、“エレイシア”と呼ばれていることも気にせず、まるで講義を受ける教え子のような振る舞いになりはじめていることにも気づいていない。
短い間とはいえ、同種の存在となった経験がそうさせているのだろう。
いや、複数の世界線の記憶が混在するせいで、微妙に頭の中が混乱しているからこそなのかもしれない。
いずれにせよ、ロアとシエルは、一介の教師と生徒のように語り合い続けた。
「並行世界の存在は確認されている。あの宝石の翁が、確認できるように“した”と言っても良いかもしれない。もっとも、あの男が定義づけた並行世界は、一般に思われているような“よく似た異なる世界が別に存在する”というものではないがね」
「確率的にしか……」
「そう、並行世界とは、あくまで観測者が現れたことで観念論的領域から唯物論的領域に浮上する仮想の概念にすぎない。つまり、並行世界とは空想具現化と同質の現象にすぎないということだ。もちろん、これは原則論としての見解であるため、何かと問題が残るのだがね」
「私が追体験した他の世界線の記憶については?」
「仮想のものと考えたければそれでも良いだろう。そもそも人の記憶など、蛋白質の配列にすぎない。こんなもので因果律が定まるなどという盲信、神秘の領域に住む者なら、笑い飛ばしておくのが健康的だろう」
「過去はひとつではない――と?」
「なぜひとつでなければならない?」
「【矛盾】するからです」
「そう、【矛盾】するからだ。しかし、この世には神秘という【矛盾】がすでに存在する。ならば、なぜ過去だけが【矛盾】してはいけない? 神秘の中には因果律そのものを改変してしまうものも少なくはないというのに」
「…………」
「エレイシア、難しく考えることはない」
ロアは優しく語りかけた。
「そもそも【矛盾】とは論理に反するという意味だ。論理とは知性。知性とは“ヒト”の魂が後天的に獲得してきた要素のひとつにすぎない」
「……因果律は?」
「存在する――と、我々の知性が判断している」
「《世界》は?」
「《世界》は観測者になりえない。《世界》はそこにあるだけだ」
「でも惑星霊がいます」
「“いる”と判断する知性が我々にあるからだ」
「……あなたは何を言いたいのですか?」
「色即是空、空即是色――ブッディズムの言葉だが、これこそ真理だということだよ」
「意味がわかりません」
「君にもいずれわかる時が来る。ただ、理屈や因果で全てを判断してはいけないということだけは覚えておくといい」
「――ロア、あなたは…………」
彼の姿が少しずつ薄らぎ始めていた。
限界が訪れたのだ。
シエルが知る神秘の“理屈”では、肉体を失った魂は長い時間、形を留めることができないことになっている。最初に肉体と魂の媒体となる精神体が崩れていき、次いで、魂も崩れていき……
――エレイシア。
ロアはシエルに微笑みかけた。
――違う道を歩めたのであれば、私は君の良い師になれたかもしれない。悔やまれることといえば、そのことだけだ。
「ロア……」
――気を付けたまえ、エレイシア。この世界は、過去に起こりえた“可能性”が、相互に【矛盾】したまま存在を許されている。不安定な“魔法”の連続使用……不完全な第二魔法で確率が歪められたところに、不完全な第三魔法が使用された。ありえない確率が“ある”ことにされてしまったのだ。神秘という【矛盾】を許した法則そのものが歪められたと言い変えてもいい。もちろん、原因のひとつはこの私だが、過去の様々な可能性の中で、生きることに執着した“意志”の幾つかが、この“【矛盾】世界”と呼ぶべき現象をつなぎ止めている。彼らを消せば、この異変を収めることができる。
「でも、だったら、あなたが消えるだけで――」
――私は執着などしていない。だから消えるのだよ。
彼は告げた。
――計らずとも君という後継者が得られた。永遠を求めた理由も、あの少年のおかげで理解できた。そして、そんな他愛の無い、笑える動機は、この胸にしまい込んだまま消えゆくべきだと……そう思えるようになった…………
ロアの躰は薄らぎ続ける。
――エレイシア。【矛盾】世界をつなぎ止める“意志”を消すんだ。もし君が知る者がいても、別物だと思え。それは無限の可能性の中で、もっとも生きることに執着した“意志”が、なんらかの力を得て顕現しただけの“現象”だ。私の時のようにためらうことなく戦うんだ。ただ……
彼は苦笑した。
――どんな時にも取り乱してはいけない。気を付けるんだ。いいね。
その言葉を最後にミハイル・ロア・バルダムヨォンは消え去った。
気配も消滅している。
だが、異なる遠い場所に別の“蛇”の気配があった。
「……なによ」
シエルはうつむいた。
怒りがこみあげてくる。
あれほど憎んだ相手が消えた瞬間、おもわず「待って」と言いそうになった。
そんな自分が無性に腹立たしい。
この怒り、どこにぶつけるべきか。
(…………………………あるじゃない、ぶつけるもの)
シエルは背負っていたアルクェイドを放り投げた。
――ドンッ!
「痛ったぁああああああ! なにすんのよぉ、このバカシエル!」
「寝たふりをして聞き耳たててる暴走超特急に言われる筋合いはありません」
「なによ! こっちが二回も心臓貫かれたのに助けにもこないし!」
「あんな怪獣大決戦に首を突っ込めと?」
「でもさぁ」
アルクェイドは服の埃を払いながら立ち上がった。
「なんか、懐かしいもの見ちゃった」
「なんのことですか?」
「さぁ?」
ニパッと笑った彼女は、両腕を後ろに回すとトコトコと歩き始めた。
「さーて、さっさと志貴と合流しなきゃ」
「……いいんですか、あの魔術師と英霊は」
「いいの、いいの。半分、成り行きで戦っただけだし。それに消さなきゃならない相手なら、志貴と合流したあとでも簡単に消せるじゃない♪」
「簡単にって……」
《朱き月》になりかけた《白き姫》と互角に争った相手を、それほど簡単に切り捨てて良いのだろうか。そういえば自分も、ロアにうながされたせいで、ついつい彼らを見逃してしまったが……
「おーい、バカシエルぅ! 置いてくよー!」
「あっ――待ちなさい、このアーパー吸血猫! 誰があんたをここまで担いで――」
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「リン、現場に到着しました。すでに戦いは終わっています」
ライダーは宝石を介して凛に語りかけた。
――真祖と代行者は?
「移動中です。追跡しますか?」
――ううん、居場所がわかればそれでいいわ。で、衛宮くんとセイバーは?
「無事です」
ライダーは足下に視線を向けた。
そこには、大の字に倒れる士郎の姿があった。セイバーは、そんな彼の左腕を枕にするようにして横向きに倒れている。というより、ライダーの目には二人が樹海のただ中で昼寝でもしているかのように見えた。もちろん、少し離れたところにあった廃墟が、跡形もなく吹き飛んでいるのだから戦いがあったのは間違い無い。
――ライダー、先輩に怪我は?
桜の声が宝石から響いた。
「見たところ、怪我らしい怪我はしていません。セイバーも同様です」
安堵の吐息が聞こえてくる。
――ライダー。
今度は凛の声。
――悪いけど、ペガサス出して、連れ帰ってくれない?
「それでは敵側に見つかる可能性があります。よいのですか?」
――いいの、いいの。どういう理由か知らないけど、二人が無事ってことは真祖が見逃してくれたってことでしょ。だったら、真祖の気が変わる前に合流して対策練っておかないとまずいわ。それに聖剣が無い以上、真祖をどうにかできる方法、ライダーの宝具しか無いってことにもなるわ。その点でも、できるだけ早く合流しておきたいの。
「わかりました。では、すぐビルの方に」
――今、下にエレベーターで移動中だからビルの前に降りてきて。
「……電気が通じているのですか?」
――自家発電が稼働してるみたい。じゃあ、あとはよろしく。
「わかりました。桜のこと、よろしくお願いします」
通話はそこで途絶えた。
(さて……)
ライダーは改めて寝そべる二人に視線を向けた。
二人とも、実に幸せそうな寝顔だ。
「………………」
とりあえず――
「……うっ………………」
数分後、士郎が目覚めた。
「んっ……」
セイバーが小さくうめいた。見ると自分の左腕を枕にして、眠るように意識を失っている。
おそらく自分と一緒に気絶したのだろう。
ただ、こうしていると、二年前のあの頃に戻ったような――
(んっ?)
右腕にも重みを感じた。
ついでに右足に何か、温かくて柔らかいものが絡みついている気がする。
士郎は顔を右へと向けてみた。
なぜか邪眼殺しの眼鏡をかけたライダーの顔がすぐそこにあった。
「おはようございます、士郎」
「なんでさ」
こうして最初の激突は、《白き姫》の圧勝で幕を閉ざしたのだった。
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.