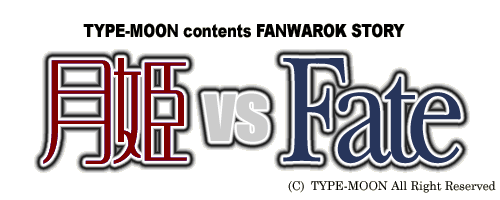
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[10]
-
5
「なんでさ………………」
士郎は激痛から、再び片膝をついた。
世界の変貌。
見たことも聞いたこともない現象――いや、違う。自分の“あれ”と同じ現象だ。
(……くっ)
左肩が痛んだ。まるで腕の付け根から無数の刃が内側から外へと突き出しているかのような激痛だ。
(そういうことか……)
士郎は痛みを堪えながら月夜の花園を一瞥した。
《白き姫》まで距離にして六十メートル。その手前には、両膝をついたセイバーが、地面から突き出た無数の鎖によって縛り付けられている。両腕ごと躰を拘束され、ガックリと項垂れているセイバーの姿は、どの記憶にも存在しない初めて見る弱々しい姿だった。
まるで罪人だ――そう思った瞬間、士郎の中に怒りが沸き上がった。
(なんでさ……)
無意識のうちに視力を魔力で補う。
セイバーの顔がハッキリと見えた。頬を伝う涙や、グシャグシャに泣き崩れている彼女の顔も――
(――ったく、なんなんだよ!)
士郎は眼を固く閉ざし、いつもの“あれ”に意識を傾けた。
瞬間、彼は莫大な光の渦の中に立っていた。遙か前方から猛烈な“何か”が吹き付け、彼の意識や存在を根こそぎ吹き飛ばそうとしてくる。だが、士郎は、その中でしっかりと立っていた。それどころか一歩、また一歩と前へと踏み出していた。
無茶だ。理性がそう叫んでいる。
確かに“あれ”は、もう衛宮士郎のものになっている。だが、肉体の魔術回路が追いついていない。毎日毎晩、この光の爆風に向き合い続けたおかげで魂の強度は充分なレベルに高まったはずだが、もしこの場で“あれ”を無理矢理使おうとすれば、肉体が限界を越え、なにがどうなるかわかったものではない。
だが――それがどうした、と士郎は思った。
壊れるなら壊れればいい。
砕けるなら砕ければいい。
すでに我が身は、我が命のためにあらず。そう在ると決め、あの時の彼女に刃を振り下ろしたのは自分自身だ。ならば今こそ、彼女を守るために――
(――俺は!)
衛宮士郎は、光の果てに踏み出した。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
(なるほど……)
《白き姫》は自らが引き起こした現象の結果に驚いていた。
確かに空想具現化を使った。
世界を作り替え、完全に騎士の英霊を押さえつけられる状態にしようと意識した。
その結果が――これだ。
途中でギョッとなったが、騎士の英霊がいる以上、アルクェイドは《白き姫》に戻ることを容認するしかなかった。少なくとも、この英霊に宝具を使う機会を与えてはいけない。なにしろ、この英霊の宝具は、“ミス・ブルー”の“魔法”やシエルの“ブラックバレル”と並びえる、自分にとって非常に厄介な代物である感じがしてならないのだ。
宝具さえ封じてしまえば、この程度の英霊はどうとでも料理できる。
そのための空想具現化だったが――まさか、ここまで“最後の一線”が後退しているとは思わなかった。
これも【矛盾】で構成された異相世界だからこその現象なのだろう。
意識を自分の内面に傾けてみる。
なるほど、修正力に対する代償としての吸血衝動が皆無に近いほど弱まっている。やはり、この異相世界では《世界》の修正力に対する代償がごくわずかなもので済んでしまうようだ。それならば真祖の兵器であった頃の《白き姫》に、これほど簡単に戻れるというのも納得がいく。
――さて。
アルクェイドならぬ《白き姫》は鎖に囚われた騎士の英霊を冷ややかに見下ろした。
――多くは尋ねぬ。答えよ。“蛇”は何処に。
だが英霊は何も答えない。
グッと歯を食いしばっているところを見ると、必至に抵抗しているのだろう。
だが、無駄な努力だ。
“
―― I am the bone of my sword () ――
「!?」
セイバーはバッと顔をあげ、左手の彼方に視線を向けた。
視界の遙か先。
月光に照らし出された花びらが舞い上がる花園の中。
ゆらりと立ち上がる赤毛の少年。
その目は、眠るように閉ざされている。
―― Steel is my body, and fire is my blood. () ――
彼の口から紡ぎ出されるのは“ありえざる記憶”のひとつでアーチャーが詠唱していた呪文だ。
だからこそ困惑した。
なぜ彼が、アーチャーの呪文を――?
―― I have created over a thousand blades. () ――
――ほぉ…………
《白き姫》は目を細めた。
―― Unaware of loss. () ――
―― Nor aware of gain. () ――
――“ここ”で妾に刃向かうとは面白い。
そんなつぶやきを受けても彼を詠唱をやめなかった。
―― Withstood pain to create many weapons, () ――
―― waiting for one's arrival. () ――
セイバーは思い出した。
これは――アーチャーだけの呪文では、ない。
―― I have no regrets.This is the only path. () ――
彼は告げた。
―― My whole life was " Unlimited Blade Works ". () ――
瞬間、紅蓮の炎の輪が広がった。
――んっ?
《白き姫》は目を細めながら右手を突き出した。
――キンッ!
彼を中心に同心円上に広がった炎の輪は、花園の半ばのところで不可視の壁に弾かれた。
だが、すでに世界の半分は彼のものだった。
無限に広がる無人の荒野。
見上げる先には真っ赤な空がどこまでも続いている。
大地に突き立つ無数の剣。
荒野にたたずむ――剣墓を守る、赤毛の少年。
「シロウ……」
囚われの少女は愛しい人を呼んだ。
応えるように、
「……吸血鬼」
衛宮士郎は、閉ざしていた両目を見開いた。
「セイバーを離せ」
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
――戯れ言を。
《白き姫》は右手を真横に振った。
花々が舞い上がる。
大地から飛びだしてきたのは、狼とも獅子とも付かぬ無数の“黒い獣”たちだった。
――逝け。
ケダモノたちは一斉に世界の境界を越えた。
「戯れ言は――どっちだ?」
士郎は左手を真横に伸ばした。ただそれでけで、その手に宝具が滑り込んだ。
「――“
刹那、稲妻が世界を埋め尽くし、“黒き獣”は一掃された。
すかさず士郎は次なる宝具を握りしめる。
右手を振りかぶり――
「――“
真名と共に渾身の力で魔槍を投げつけた。
――笑止。
《白き姫》はすかさず真横に振り抜いた右手を、前へと突き出した。
刹那、世界と重なり合うように半透明な分厚い城壁が出現する。
“
物理的に存在せずとも、その概念だけあれば“在る”と同じ意味を持つ――それが幻想で紡がれた世界の法則なのだ。だが、一言の詠唱すら無く、概念を概念のまま自由自在に操る《白き姫》の力量は常軌を逸しているとしか言い様が無い。
「うぉおおおおおおお!」
士郎は雄叫びをとどろかせながら、自らが放った幻想に“障害を突破するイメージ”を上乗せした。
魔槍は赤い烈光を放ちながら城壁に突き刺さる。
だが、城壁という概念はびくともしない。
――ふむ。
《白い姫》は不快そうに目を細め、手首を返した。
世界がぐにゃりと曲がる。
魔槍が城壁に吸い込まれる――が、同じ場所から真紅の赤光が飛び出していった。返し矢ならぬ返し槍、《白き姫》は空間ねじ曲げ、魔槍を投げ返したのだ。
だが、士郎に慌てた様子はなかった。それどころか、自ら刺されに行くかのように、迫る魔槍に向かって駆け出してさえいる。
両手には瞬時にたぐり寄せた夫婦剣――干将と莫耶。
――んっ?
と《白き姫》がいぶかしんだ頃にはもう遅かった。
魔槍が消えた。いや、ありえない動きで軌道を変え、《白き姫》の眼前に出現していた。
幾たびかわされようと相手を貫く――それがゲイ・ボルグの真骨頂。
閃光が《白き姫》を貫く。彼女はグラリと躰を揺らがせた。
だが、倒れはしない。顔こそ伏せたが、わずかに左足を踏み出し、ふんばっている。
それでも貫かれた左胸から、真紅の鮮血が前後に噴き出した。
どう見ても致命傷だ。
(よしっ――)
と士郎が勝利を確信したのも当然だろう。
あえて英雄王の真似事をしないのは、囚われのセイバーを巻き込まないためだ。一瞬でも早く、こちらを呆然と見ているセイバーを助け、圧倒的な宝具の飽和攻撃で止めを――
――見事。
不意に《白き姫》の姿がかき消えた。
――誉めてつかわそう。褒美だ。
瞬間、士郎は無意識のうちに足で地を削り、急制動をかけた。同時に、干将と莫耶を逆手に持ちかえ、両腕を交差するようにして頭部を守ろうとする。
意識しての動作ではない。本能的な行動だった。
直後、圧倒的な衝撃が全身を揺さぶる。
なにがどうなったかわからないまま、士郎の躰が荒野の奥へと吹き飛ばされた。
――これも防ぐか。
《白き姫》は感情のこもらないまなざしで吹き飛ぶ士郎を見送っていた。
(ミスった――)
容貌だけで判断してしまった。深窓の姫君にしか見えない外見だが、だからといって間接攻撃型だとは限らない。士郎は知らないことだが、《白き姫》は真祖殺しの真祖だ。セイバーとの戦いで見せた通り、その真骨頂は――
(――ったく、この
荒野に躰がバウンドした直後、士郎は干将と莫耶を交差するように投げ出した。
だが《白き姫》は気にすることなく直線的な突進を再開する。
迫る干将と莫耶。
だが夫婦剣は、《白き姫》に触れる寸前、不可視の壁に弾かれてしまった。
なるほど、受ける必要も弾く必要も、ましてやかわす必要すら無いらしい。
想像以上の化け物だ。
「――つっ!」
士郎の躰が再び地面を跳ねようとする。そこに《白き姫》が迫った。
躰を捻り、右腕を地面に叩きつける。
その衝撃を使い、士郎は膝立ちの姿勢になりつつ、後ろ向きに地を滑りだした。
(今度は――!)
干将莫耶の再剣製。
消える《白き姫》。
見えた。
頭突きをするように突き進んでくる、無骨なまでの《白き姫》の突進――そこに士郎は双剣を重ねた。
命中。だが、刃は届かない。
不可視の壁だ。
セイバーのように風によるものではない。《世界》そのものを、そうあるよう作り替えている絶対不可侵の壁だ。
勢いも殺せない。そのまま士郎の両足はガリガリと地面を削りつづけた。
――なるほど。
わずかに離れた《白き姫》は、瞬きの瞬間に八つの拳を繰り出した。
「!」
士郎はその全てを干将莫耶で弾いた。
――守りに特化した剣術……いや…………
続けざまの十二の拳。士郎はこれさえも全て弾いた。
――目か。おぬし、我が動き、見えておるのだな。
十六の拳。
弾き、避け、いなす――いや、いなせず、よける。
――面白い。一の動きで百を予測するとは……しかし、これはどうだ?
刹那、視界が金色に染まった。
縦横無尽な《白き姫》の動きに長い金髪が広がったのだ。
同時に繰り出された拳と蹴り足、その数、百と八つ。
されど多重次元屈折現象でも無い限り、全ての動きは一から始まり、有限で終わる。
ならば防げぬ道理はない。
光爆の彼方にたどりつきし衛宮士郎は、刹那の間なら英霊エミヤと同格になれるのだから。
「――!!」
士郎は全てを受けきった。神技だ。いや、英霊エミヤの技はヒトがヒトのまま到達しえる極みのひとつにすぎない。ゆえにこれは神技ではない。だが、英霊ならざる人の身で、それを為し遂げてしまった代償は決して小さくはない。
唇の端からは血が溢れ出た。
全身の筋肉繊維も悲鳴をあげていた。
(次が来たら――)
確実に躰のどこかが壊れる。そうなれば、もう終わりだ。この規格外の怪物が、そんな隙を見逃すはずなどないのだから。
――ほぉ、これも防いだか。
怪物がつぶやいた。
――では……本気でいかせてもらう。
(………………)
驚きの言葉すら思い浮かばない。
(最初から……)
間違っていた。“これ”は、決して真正面から争ってはいけない“もの”だった。
いや、その程度のことは自分だって最初から気がついていた。本能がそう告げていたのだ。しかし、だからといって逃げられるわけがない。そういう人間なら、そもそもこんな怪物にめぐり合うことすら無いはずだ。二年前の“あの戦い”でも――
(――あっ)
士郎は自らの愚かさに気が付いた。
(“これ”があるだろ!)
自らに言い聞かせながら左手の甲に意識を流し込んだ。
刹那――
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
鎖につながれたセイバーは士郎と《白き姫》の激闘に目を丸くしていた。
(シロウ……?)
あろうことか士郎は《白き姫》の攻撃を受けきっている。
信じられない。あれは人の域を超えた動きだ。自分ですら万全でなければ受けきることができない攻撃だ。それを士郎は人の身で成し遂げてしまった。驚くなというほうが無理な相談だ。
(何時の間に――)
彼女は士郎がアーチャーを受け継いでいることを知らない。士郎が左腕を失ったことも、アーチャーの左腕が移植されたことも知らない。辛うじて覚えているのは、最後の戦いの前、誓いを破りかけた自分を止めてくれた士郎が、なんらかの手段で限界を超えた“何か”を持っていたということぐらいだ。
(――あっ!)
不意に別の世界線の記憶がよみがえってきた。
それは自分が良く知る五軸目の世界線の枝葉。士郎がライダーを伴わず、凛と二人だけで地下洞窟に赴いた時の記憶だ。
結果的に限界を超えてしまい、完全に壊れてしまったが――衛宮士郎は全力のセイバーと真正面から激突し、あまつさえ、戦いに勝利した。今のセイバーは、その時のことをハッキリと思い出すことができる。
士郎は宝具“干将莫耶”の真の力を引き出した。
その一瞬、彼は人の身で英霊を超えた。
ただ、同時に彼は壊れた。
覚えている。
並んで倒れる自分と士郎。自分が回復する前に止めを刺すよう告げてみたが、隣に倒れる士郎の瞳には、意識の輝きが欠片も残っていなかった……
(――ダメ!)
セイバーは全身に力を込めた。
鎖がきしみをあげる。
(シロウが、壊れる!)
せっかく夢の続きを見られたというのに。
士郎が、壊れる。
「――うぁあああああああああああ!」
彼女は叫び、鎖を引きちぎりにかかった。
莫大な魔力が放出される。
直後。
――セイバー!
士郎の声無き叫びが脳内に響いた。
(シロウ!)
虹色の魔力が爆発した。次の瞬間、セイバーは《白き姫》の真後ろに出現していた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
――転移?
《白き姫》は彼女から見て右手の方向に飛び退こうとした。だが、同じ速度で背後に瞬間転移してきた存在概念――騎士の英霊も追撃をしかけてくる。
「はっ!」
騎士の英霊――セイバーは不可視の剣を振るった。
――愚かな。刃はすでに――
背中が切り裂かれた。
――!?
セイバーの剣は刀身で切り裂くわけではない。刀身を隠す風の鞘――《
しかも、
「“
続けざまに士郎の声が響き、
「――――“
必殺の魔槍が繰り出された。
――くっ。
《白き姫》は世界を曲げた。そのまま“
間に合わない。
愕然とするより先に魔槍が心臓を貫いた。
――くっ!
より強く世界を曲げる。世界の歪みは槍を残したまま《白き姫》の躰だけを“
自己修復開始。
状況分析、根源認識開始――失敗。
(――んっ?)
《世界》は今だ、不安定なままだ。少しずつ薄らいでいる感覚も変わっていない。おかげで簡単に幻想を広げられたが、根源認識が不確実なままだ。そのうえ、
今は騎士の英霊が放出した莫大な魔力のおかげで大丈夫だが、下手に
それでは意味がない。自分は《白き姫》のまま遠野志貴に再会しなければ……
「シロウ!?」
「……だ、大丈夫」
剣墓の荒野では倒れ込む赤毛の魔術師を騎士の英霊が支えようとしていた。
強い絆があるらしい。
おそらく、それが英霊召喚の原因だろう――と《白き姫》は推察した。
(でも――)
と彼女は思考を進めた。
この異変をおさめるには【矛盾】の量を《世界》が許容できるレベルまで落とさなければならない。そのためには異変の根幹に関わっている可能性が高い“蛇”を消せば良いはずだ。つまり騎士の英霊や赤毛の魔術師など捨て置いてもかまわないのである。成り行きから戦いになってしまったが、それも可能性の問題として、異変の引き金となった騎士の英霊は消しておいた方がよいと判断したためだ。つまり、必ずしも戦う必要は無かったのである。
だが、今は別の考えが《白き姫》の思考を揺さぶっていた。
(確かめずに立ち去っても良いのか――?)
それは《朱き月》の思考だった。
騎士の英霊は危険な存在だ。もともと“霊長の抑止力”とは無形の突破力。その多くは“ひらめき”という名の、時代を超えた知識という形で発現する。そうでない場合は特定の英霊に宿る特質をコピーした魂が生み出され、これを宿した人間が生まれ、活躍することで危機の解決にあたる。つまり“霊長の抑止力”とは、本来、それが抑止力であると知られない形をとるのが通例なのだ。ゆえに抑止力の具現体である英霊の顕現は極めて異例な出来事といえる。いや、むしろ本来はありえないと言い切るべきだ。
しかし、今は目の前に英霊が顕現している。
しかも騎士の英霊は単なる“霊長の抑止力”に留まっていない。その存在概念に“竜”を宿す“世界の抑止力”でもある。
騎士の英霊が背負う《世界》は
《朱き月》が背負う《世界》は
遙か昔、《朱き月》は“魔法”を知らないがゆえに敗れ去った。いや、知ろうと思えば知ることができた。しかし、それほど重要なものだとか考えなかった。だからこそ、《朱き月》は敗れたのである。
同じ過ちを繰り返してはいけない――《白き姫》の中の《朱き月》がそう告げていた。
見極めなければならない。
“霊長と地球の抑止力”と、その召喚主たる不可解な魔術師に、あの宝石の翁のように《朱き月》を止められるだけの力があるのかを。
(ならば――!)
すでに器の半ばまで《朱き月》に満たされてしまった《白き姫》は、黄金色の瞳を輝かせながら、高々と、その右手を天空に伸ばした。
突き立てられた人差し指の遙か先には、静かにたたずむ朱色の満月が輝いていた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「シロウ!?」
「……だ、大丈夫」
駆け寄るセイバーに、士郎は笑顔を向けようとした。だが、それで張りつめていたものがプツリと切れてしまったらしい。足から力が抜け、荒野に膝をつきそうになる。そんな彼の躰を、瞬時に駆け寄ったセイバーが真正面から抱き支えた。
「シロウ!? しっかりしてください!」
「大丈夫……だって」
「強がらないでください!」
「本当だって……そうだ、言ってなかったよな……俺の躰、生身じゃないんだ……人形の躰に魂を移しただけで……」
それでもセイバーが支えてくれなければ、今にも倒れそうなほど躰がボロボロになっている。
自惚れていたかもしれない――士郎はそんなことを考えた。
この素体を使うようになって約一年半、すでに躰の性能は生身の人間を遙かに超えている。セイバーの相手は無理だとしても、宝具を封じたライダーが相手なら戦闘力は五分だ。いや、守りに関していえば、ライダーですら今の自分の相手にもならない。
万撃を防ぐ鉄壁の守り。
“正義の味方”を目指した男が会得した究極の戦闘技術。
未来の自分を内包した衛宮士郎は、今、そのさらに先へと進もうとしている……
だが、絶対に破られない盾などあるはずがない。
このままいけば、完全に――そう思った、その時だった。
脅威を感じた
あの白い脅威が突進してきた時と比較にならない、あまりにも純粋すぎる、万物を押しのけてしまうような“脅威”の概念が突如として押し寄せてきた。
「月が――!」
セイバーが叫ぶ。士郎も、同じものを見た。
ほぼ同時に、《白き姫》は振り上げていた右手を振り下ろす。
――逝け。
士郎たちに向けられた指先から、ドンッと“月”という存在概念そのものが打ち出された。
ムチャクチャだ。
地球より小さいとはいえ、天体の存在概念を
非常識にもほどがある。
だが、非常識という意味ではこちらも負けてはいない。
「セイバー!」
士郎は左脇に肩を入れているセイバーに視線を向けた。
驚愕のあまり顔を青ざめさせたセイバーが目を見開いたまま士郎を見上げてくる。
「返す前に、使うぞ!」
彼女は最初、何を言われたのか理解できずにいた。
しかし、言葉の意味を正確に理解し、さらに目を見開いた。
「まさか――いえ、使ってください! 返す必要はありません! シロウのものです! シロウは、私の鞘だから――!」
もう時間が無い。
シロウは右手を突き出した。まるで申し合わせたように、セイバーも左手を突き出す。
彼は“それ”を投影した。
いや、投影する必要すらない。それは深く彼の魂と結びついたものなのだから!
「「 “全て遠き理想郷 () ” 」」
二人は同時に真名を叫んだ。
直後、ふたつの世界が衝突した。
真紅と黄金の激突。
月そのものが抱く幻想と、幾多の霊長が現在進行形で紡ぎ続ける理想郷という名の幻想――その衝突は、世界を光で満たしていった。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.