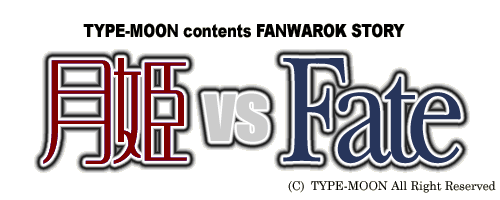
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[12]
-
1
目覚めた瞬間、“彼女”は悲鳴をあげていた。
断末魔の残滓だ。
しかし、それもすぐに収まってしまう。
「――――――」
気が付くと薄汚れたビルの谷間に倒れていた。
仰向けに倒れているせいで、左右にそそり立つ灰色の壁と、その彼方に垣間見える重々しい曇り空とを見ることができる。
(ここ……どこ…………?)
見慣れた場所の気がする。同時に初めての場所のようにも思える。
わからない。
わかることは――ここが三咲市の繁華街では無いような気がするということ。
とりあえず上体を起こし、周囲を眺めてみる。
やはり記憶にない場所だった。そうだとわかった瞬間、先程まで脳裏を埋め尽くしていた圧倒的な恐怖が思い出されてしまった。
“彼女”は再び悲鳴をあげそうになった。
同時に、ひどく混乱した。
おかしい。
どうして自分は、こうして残存しているのか。
なぜ見逃されたのか。
なぜ無事なのか。
ここは
今は
おかしい。
わからない。
なぜ? どうして? 今はいつ? ここはどこ? なんで消えてないの? どうして自分は、自分だとわかるの?
「………………」
“彼女”は立ち上がった。
サラリと髪が流れる。長い髪を左右で束ねていたリボンが、その拍子にハラリと地面に落ちた。“彼女”はリボンを拾おうと躰を屈め――ようやく、制服がひどく汚れていることに気が付いた。よく見ると、腹部には大きな穴まで空いている。
いや、当然だ。
そこには、あの“白い悪夢”の腕が突き刺さったのだ。
正確には、腹部全体が、腕のひと突きで吹き飛んだのだ。
とどめは頭部の圧壊。
あの“白い悪夢”は、空き缶を踏みつぶすように、グシャッと、簡単に踏み砕いた……
しかし、自分は生きている。いや、もともと死んでいるのだから、生きているのは不適切だ。やはり残存したと表現するべきだろう――そんなことを考えながら、“彼女”は赤黒く汚れた両手でリボンを拾い、髪を整えた。
髪型はツインテール。
子供っぽい。でも、どうしてもやめることができない。
「……志貴くん…………」
懐かしい名をつぶやいてみる。
心が高鳴った。
口元に、幼児のごとき無邪気な笑みが浮んだ。
「待ってて、志貴くん……わたし、
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
(――問題は最低でも七つあるってところよね)
遠坂凛は、エレベーターの階数表示を見上げながら、改めて自分の推測を検証してみた。
現象そのものは珍しいものではない。だいたい、原理は固有結界とまったく同じだ。違いといえば、主客が《世界》であるということぐらいだろう。そういう意味では、精霊や悪魔などの固有結界に近いのかもしれない。
あえて名を与えるとすれば――“
《世界》の修正力が極度に弱い隔離世界だ。
ここでは、様々な矛盾が容認されている。
たとえば空飛ぶ靴で飛翔しながら、実はペガサスに跨っているという“事実”が許される。死に場所が多岐に渡るという“事実”も許される。赤の他人が真名の前に神名を加えることで、すべて同一人物となり、ひとりの男が複数の妻を持っているという“事実”も許される……
さすがにそこまでひどくはないだろうが、この
(まったく……どうしろっていうのよ)
まるで不思議の国に迷い込んだアリスの気分だ。
だが、なにもかもわからないわけではない。
異変が冬木市で起きた以上、あの《大聖杯》が関係していることは間違いないはずだ。
それともうひとつ――“魔法”が関与していることも確実と見ていいだろう。
そこから導き出される仮説とは、聖杯戦争において七騎の
あくまで、仮説にすぎないが。
(でもねぇ……)
根源認識力で読みとる限り、今の《世界》は七つの奇妙なシンボルで括られていた。
シンボルはそれぞれ――“蛇”、“剣”、“砂”、“蟲”、“獣”、“書”、“墓”。
統一性や象徴性の欠片も無い並びだ。
(“剣”はセイバーのことだろうし……“蟲”は、あのジジィよね)
他のシンボルは見当もつかないが、あの老人を自らの手でぶん殴れるかもしれないというのは、ある意味において嬉しい誤算だ。
(そうじゃなくて……)
凛は考えを切り替え、異変の原因について考えてみた。
聖杯戦争とは、マナを蓄積した《大聖杯》を用い、七騎の英霊を“限りなく本体に近い状態”で召喚したあと、肉と霊を失った彼らが“向こう側”に戻ろうとしたところを《小聖杯》にトラップし、ため込んだ“戻ろうとする英霊”を一気に解放するによる突破力を利用して“向こう”と“こちら”を結びつけるパイプを生み出し、《根源の渦》そのものを具象化する――という壮大な魔術儀式だ。
このうち、マナの部分を矛盾に変えてみるとどうなるだろうか?
水が一滴ずつしたたるように、“なにか”に矛盾が溜まったとすれば?
それが“なんらかの現象”をキッカケに解放されたとすれば?
(でも、《大聖杯》は存在しないし……《小聖杯》だって…………)
凛はちらりと肩越しに後ろを見やった。
背後では桜がずっとうつむき続けている。ライダーには「ストライキ中」とだけ言っておいたが、実はそれ以上に事態は深刻だ。
(なにしろ……セイバーだもんねぇ……)
凛は再び階数表示を見上げながら小さく溜息をついた。
最初こそ気にしていないようなそぶりを見せていたが――桜はセイバーに対して強い負い目を抱いている。
士郎とセイバーを引き離したのは彼女だ。
殺し合いまでさせたのも桜本人だ。
そのうえ、士郎は自らの手でセイバーを殺したことを、長く引きずっていた。
この一年でどう変わったか確かめていないものの、完全に吹っ切れたと考えるのは、あまりにも楽観的すぎる。むしろ、彼の性格を考えれば、死ぬまで悔やみ続けていると見るほうが正しいだろう。
(まったく……どうすればいいのよ)
こうなってくると、セイバーを抱いた士郎に対し、理不尽な怒りがこみ上げてくる。
いや、合理的な怒りだ。
妹の彼氏が浮気をしたのだ。どんな理由があるにしろ、怒るのは当然のはずである。
(そうよ、怒って当然よ!)
凛は怒りの理由をそこに見いだした。
他にも理由がありそうだったが、そこはあえて考えないようにした。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「でも秋葉さま、近親相姦そのものを罰する法律なんて無いじゃないですか。そりゃあ、結婚しているなら『婚姻関係の継続が困難となる状態を作り出した』とか言われちゃいますけど、志貴さまはまだ独身ですし、ここは思い切って、ズバーっと」
秋葉は琥珀を無視して歩き続けた。
琥珀がこの手の話しを切り出してきて、すでに三十分が経過している。
最初のうちは怒鳴り返していた秋葉だったが、もはや無視するしかないと決め込んだようだ。そうしたわけで、秋葉は
――待ち続けても無意味だから手近なところを探し回る。
という言い訳を大義名分(?)に、駅前広場を早足で離れてみたのだが――案の定、琥珀は秋葉に劣らぬ早足で歩きながら、飽きもせず、例の話題を語り続けていた。
「あっ、お恥ずかしいのでしたら、お酒の勢いというのはいかがですか?」
ちなみに秋葉は今年で十八歳だ。
「それとも一服盛りますか? 志貴さん、記憶を無くして野獣のように秋葉さまを――そうですよ。志貴さん、普通の時もケダモノですし、いいと思いません?」
なぜ“普通の時”を熟知しているのか?――と尋ねたかったが、秋葉はやめておいた。
やぶ蛇というか、恐いことになりそうな気がする。
「秋葉さま?」
無視。
「隠し金庫の……」
「!?」
秋葉は立ち止まるや否や、顔を真っ赤にして振り返った。同様に立ち止まった琥珀は、ニコニコと微笑み返すだけである。
「……琥珀、“
「私がネコですか? どちらかといえばタチだと思いますけど」
「………………」
「すみません。誤解していました。秋葉さまがそういうご趣味なら――」
「そんなわけないでしょ!」
秋葉は背を向け、再びズカズカと大股で歩き出した。
どうもおかしい。
異変が起きてからというもの、琥珀は前にも増して積極的になった気がする。
(……そうよね)
考えてみれば当然だ。記憶の中だけとはいえ、琥珀は心の奥底に秘め続けていた“復讐”を果たしてしまったのだ。それがどれほど、琥珀にとって重要なことだったのか、秋葉には想像すらできない。
「――琥珀」
「はい、なんでしょう」
「そんなに私と兄さんを結びつけたいのは、どうして?」
「高校を卒業なされたらどうされるおつもりですか?」
逆に琥珀が尋ねてきた。一瞬、秋葉は立ち止まりそうになるが、できるだけ平静を装いつつ、黙々と足を運ばせ続ける。
「秋葉さま?」
彼女の後ろを、琥珀が追いかけ続けた。
その後、しばらくの間、二人は無言のまま無人の街を歩き続ける。遙か彼方にそびえ立っていた、この街で最も高いインテリジェンスビルらしき場所へと少しずつ近づいていく。なんとくなくだったが、秋葉は、そこが終点だろうと感じ始めた。
いずれ言わなければならないことだ。
自分の将来。遠野家の当主である、遠野秋葉のこれからの人生。
「秋葉さま」
今度の呼びかけには、両足が勝手に応えてしまった。
気が付くと足下ばかり見据えていた。灰色のアスファルトからスッと視線をあげていくと、五十メートルと離れていない先に、厚くたちこめる暗雲を背負った巨大なガラスの墓石がそそり立っている。
「……そうね」
秋葉はポツリとつぶやいてから、振り返った。その先にいる和服姿の琥珀は、先程と同じ満面の笑顔のままだ。
「琥珀はどうして欲しいの?」
「私は秋葉さまの使用人です」
即答だった。
不覚にも秋葉は、琥珀から顔を背けてしまった。
「……バカじゃないの?」
「ほら、ペットは飼い主に似るといいますし」
「……誰がペットよ」
「やっぱり私がタチですか?」
「そうじゃなくて――」
刹那、琥珀が力強く秋葉の腕を引っ張った。
あまりにも不意の出来事に、秋葉はバランスを崩した。
「こ――!?」
琥珀に抱きしめられながら、歩道と私有地を分かつ植え込みの陰に倒れ込んでいく。背中を歩道の石畳に打ち付けたせいで息が止まり、それ以上に声をあげることができない。
途端、琥珀の右手が秋葉の唇を塞いだ。
「お静かに。敵です」
「!?」
見ると琥珀は、押し倒したに覆い被さりながら、植え込みの茂みの隙間を見据え、あの暗雲を背負う巨大な墓石――この街で一番高いインテリジェンスビルの方向を観察していた。
「志貴さんたちが居なくなる寸前のこと、覚えていらっしゃいますか?」
秋葉は小さく首を横にふった。
「あの時、アルクェイドさまたちが戦っていた相手がいます。護衛を務めていた者はいません。二十歳前後の女性ふたり。アルクェイドさまとシエルさまが狙っていた人物です。おそらく、今回の出来事の中心に近い立ち位置にいる人物だと思われます」
「……そこから見えるの?」
秋葉は琥珀の手をそっと押しのけつつ、仰向けになったまま小声で尋ねてみた。
「気を付けてください。頭を出さないように」
「髪、抑えて」
二人は植え込みから頭を突き出さないよう注意しながら姿勢を変えた。共にしゃがみながら、秋葉が前、琥珀が後ろという並びである。
「……あれね」
「はい」
確かめるまでもない。インテリジェンスビルの正面玄関の前に、見知らぬ二人の女性の姿があるのだ。片方は赤い上着に黒いロングスカートを履いた黒髪の凛々しい女性。もう片方は白いブラウスに空色のロングスカートという濃紺の髪の儚げな女性。一見すると対照的に見えるが、それだけに二人には奇妙に似通った雰囲気があった。
「姉妹?」と秋葉。
「姉妹ですね」と琥珀。
「……本当にあの二人だったの?」
「間違いありません」
「そうだとしたら厄介な相手よ……」
「ご存じなんですか?」
「黒髪の方よ。琥珀なら聞いたことあるんじゃない? 遠坂の天才魔術師の話」
「秋葉さま、私が知っていることは過去のことと遠野家の中のことだけですよ?」
「……とにかく、最も“魔法”に近いとか五大元素を操るとか、いろいろと言われている天才的な魔術師がいるの。あれがそうよ。名前は遠坂凛」
「つまり、街中の人間を一気に消すことができる人間――ですか?」
「そうね……あくまでも可能性の話だけど、この街にいる人間、私たちとあの二人だけって可能性は?」
「否定できません。どうして秋葉さまと私だけなのかという疑問も残りますが、それでも、あの二人が何かを知っている可能性は高いと思います」
「友好的に対話で解決できると思う?」
「難しいですね。アルクェイドさまが問答無用で襲いかかったみたいですし」
「先手必勝で潰すしかない相手だってこと?」
「英霊の話をされていましたよね? 多分、相性の悪い相手なのだと思います」
「……私も?」
「否定できません。ですが、向こうはこちらのことに気づいていません。それに、ここには私がいます」
琥珀は秋葉の耳元で囁き続ける。
「時間の経過が今の私たちにメリットとなるのか、デメリットとなるのか――それはわかりません。このままやりすごし、待ち続ければ状況が改善する可能性もあります。しかし、その逆の可能性も否定できません。ご決断下さい。どちらを選ばれても、全力で補佐致します」
「待つのは嫌いよ。知ってるでしょ?」
「はい、もちろん」
微笑んだ琥珀は、秋葉の躰に腕を回すと、彼女の顔を横に向かせ、自ら少し身を乗り出すようにして――唇を重ね、舌を差し込んだ。
口腔に溜まる唾液を秋葉に送り込み。
秋葉の口腔の唾液を飲み込み。
再び琥珀の唾液を秋葉が飲み込み、秋葉の唾液を琥珀な飲み込み……
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.