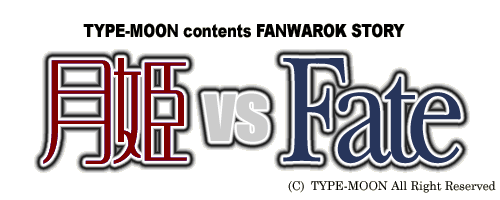
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[09]
-
4
「とりあえずその話は落ち着いてから……な?」
という誤魔化しの言葉でセイバーを落ち着かせることに成功した。
「わかりました」
セイバーは胸元に手を当て、しばし、深呼吸を続けた。
「――もう大丈夫です。シロウ、命令を」
再び目蓋を開けたセイバーの表情は“勇猛なる騎士の王”のものに切り替わっていた。
少しだけ士郎は胸の奥に痛みを覚える。思い出されるのは、セイバーに凶刃を振り下ろしてしまった記憶だ。二年という月日のせいでボンヤリとしか思い出せないはずだったが、今はどういうわけか、あの時の手応えすら思い出すことができる。
(あんなことしておいて……)
“ありえざる記憶”に引っ張られたとはいえ、セイバーを再び抱いてしまった。
欲望に身を任せた自分は、なんと汚らしい人間なのだろう…………
「シロウ?」
「…………ごめんな、セイバー」
「?」
「あの時は…………」
その一言で、ようやくセイバーも洞窟での死闘の事だと理解したらしい。
「謝る必要はありません。むしろ、謝るべきなのは私です」
「えっ? いや、でも……」
「私は“シロウの剣になる”という誓約を破りました。あまつさえ、あなたを殺そうとしました。それをシロウは止めてくれたのです。シロウが……シロウが止めてくれなかった“記憶”の中の私は、そのまま消え入りそうなほど深く後悔しています」
セイバーは両手を胸に押し当て、しばらくの間、黙り込んだ。
不意に彼女の口元が緩む。
「おかしいですね。【矛盾】した存在の私が、確定した世界線のことを話しているなど……」
「……そうか?」
「召喚された時、最初に思い出したのはシロウと共に最後まで戦った世界線の記憶です。あなたに殺してもらえた記憶は、あとになって思い出しました。もしかすると、ここにいる私はその世界線の“私”であって、あなたに殺してもらえたセイバーは――」
「どちらも君だよ。この世界では」
突如、廃墟に第三の声が響いた。
「なっ――!?」
「シロウ、後ろに!」
セイバーは無銘の名剣を不可視の状態にしつつ“後の先”をとる右下段に構えをとった。当然、士郎も退くことなく、彼女の隣で、右足を前に踏み出す“鉄壁の構え”をとっている。
二人が躰を向けているのは、ライダーが飛びだしていった、あの窓辺だ。
そこに立つのはひとりの青年だった。
漆黒のズボン、裾を出した白いYシャツ、黒いベストは前ボタンを全て外し、シャツの襟元もボタン三つ分、ゆるめている。その隙間から垣間見える肌は病的なまでに青白く、生気が感じられない。痩せこけた頬も同様だ。背の中程まで伸びた波うつ黒髪が、まるで生きた“蛇”のように身をくねらせながら顔の右半分を隠している。
「私が保証しよう。君は間違いなく、確定した世界線に存在している。“あれ”から染みだしたのは、この私を含めて七名のみ……おそらく七という数字は基盤となった儀式に関連しているのだろう。もっとも、私はオマケにすぎないのだがね」
黒と白で形作られたモノトーンの青年は、左の瞳で二人をけだるそうに見つめてきた。
二人は背筋に悪寒を感じた。
蠱惑的な眼差しだ。魔眼ではないが、青年の黒い瞳には魔的な魅力が宿っている。
「……あんた、誰だ?」
士郎はいつでも干将莫耶を投影できるよう意識を絞りながら
青年は考え込むように顎をわずかに引き、目を閉ざした。
「難しい質問だ」
「悪いが冗談に付き合ってる暇は無いんだ」
「気を悪くしたのなら謝る。しかし、今の私が“
青年は
「……セイバー、わかるか?」
士郎は小声で尋ねた。
「死徒です」
セイバーは謎の青年に全神経を集中したまま端的な言葉で答えを返した。
(あれが……)
初めてみる吸血種の姿に士郎は奇妙な感慨すら覚えてしまった。
この世には俗に吸血鬼と呼ばれる超越種が実在している。正確には吸血種だ。“
まず吸血種に血を吸われた生物は、腐敗する肉体を他の生物を喰らうことで補う“
次いで、肉を喰らわずとも肉体の維持が可能なレベルになると“屍喰鬼”は“
ただ、稀に人間だった頃の記憶を取り戻せる者がいる。これが本物の“
しかし、これが最高段階ではない。
より高みへと昇った“吸血鬼”は“死徒”と呼ばれる超越種として闇の世界に君臨することになる。その御座はわずか二十七座。神秘に関わる者たちの間で、“死徒二十七祖”に関わるといえば死を意味するとさえ囁かれている……
だが、“生きる屍”に始まり“死徒”に至る階層も、しょせんは後天的な吸血種という枠からはみ出ることはない。
先天的な吸血種。
全ての夜の者の頂点に君臨する者――それを“真祖”と呼ぶ。
(あの白い脅威は真祖……こいつは死徒……聖杯戦争の次は吸血鬼かよ……)
士郎の口元に浮かぶのは自嘲の笑みだ。
よほど騒動に好まれているらしい。
恐怖や不安が無いわけではない。だが、士郎はすでに“死”すら生ぬるい経験を積んでいる。移植したアーチャーの左腕に侵蝕され、魂が砕かれていった経験すらあるのだ。その上、今の士郎はセイバーと共に戦った時の記憶、“
あれに勝る脅威は存在しない。
死徒にしろ真祖にしろ、彼らに出来ることは――自分を殺す“だけ”だ。
「……ふむ」
謎の青年は腕を組みつつ、左手で自らの顎を撫でた。
「君たちは私と戦うつもりのようだが……それで間違いないかね?」
「できればこのまま穏便に別れたい……かな?」
「なるほど」
青年はうなずく。
「では、そうしよう」
途端、青年の姿は霧になった。
同時に、世界を揺るがすほどの轟音と共に、廃墟の窓辺を砕き、白い脅威が突進してきた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「とりあえず志貴と合流――」
と告げた瞬間、アルクェイドの目が険しさを宿した。
シエルも同じものを感じ、“黒鍵”を具現化させながら、バッと背後に体を向ける。
“蛇”の気配。
距離こそあるが、“蛇”の気配が忽然と、把握できるほどの明瞭な濃度を持つようになっていた。
(あいつ――!)
アルクェイドは駆けだした。
踏みだしの一歩で地面が大きく抉れ、衝撃波と土砂がシエルに襲いかかる。
「馬鹿――!」
一瞬だけ出遅れたが、シエルもその後を追った。
だが、圧倒的なまでに速度が違う。
(まさか――)
“蛇”が復活したことで、ただでさえ人外の域にあるシエルの身体機能も一気に向上している。時速百キロを超える猛速度で地を駆けることすら可能だ。しかし、それですら猛然と飛びだしたアルクェイドに追いつかない。
時速に換算すれば、軽く三百キロ以上出ているだろう。
必勝を狙ったのだ。
今のアルクェイドは、普段は九割、有事の際でも七割の力を費やして封じている吸血衝動すら解放しているのだ。
全力を出したアルクェイドに敵う者などいない。
なぜなら彼女は“世界の抑止力”が体現した存在なのだから――
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
謎の青年が立っていた窓辺へと突進してきた白い脅威――だが、絶対止められないはずの爆走を、床板を踏み砕いた青い閃光が不可視の剣で真っ向から受け止めていた。
(――英霊!?)
アルクェイドは一瞬にして相手の正体を把握した。
瞬間、意識が“殲滅”一色に塗りこめられた。
青い騎士は英霊だ。それもただの英霊ではない。ガイアとアラヤ、共通の抑止力として考えられる最高のスペックを与えられた英霊だ。しかも青い騎士は、どこからともなく莫大な魔力の供給を受けている。そのうえ、供給された魔力を自らの中で爆発的に増幅させている。
魔術回路など足下にも及ばない魔力錬成量だ。
あれは魔術炉心――虹色の魔力を無尽蔵に練り上げていく、自分と同格の怪物だとアルクェイドは認識していた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「うわっ!」
情けないことに士郎は白と青の激突の衝撃波で廃墟の外まで吹き飛ばされてしまった。
壁を砕き、廊下を飛び抜け、さらに壁を砕いて外へと投げ出される。そのうえ彼は、二度、三度と地面をバウンドしていた。
(――もとの体だったら四回死んでるぞ!)
今の士郎の躰は生身ではない。封印指定すら受けた魔術師の手による高品質の素体をベースにした特殊な体だ。もっとも、あまりにも精巧すぎるせいで、普段は生身同然の性能しか発揮されない。だが、いざという時には魂の有りように応じ、器としてのスペックが飛躍的に向上してくれる。
つまりどういうことかと言えば――異常に頑丈になった、ということだ。
だが、血も流せば骨も折れる。
今も肋骨が七本、もってかれた。
あの衝撃でその程度に済んだということ事態、異常と言えば異常なのだが、現状を考えれば致命的な怪我と言うしかない。
これではセイバーの足を引っ張る。だが、彼女にだけ、戦わせておくわけにはいかない。
相手は白い脅威――多分、あの時の“真祖”だ。
「くっ――!」
歯を食いしばり、口に入った砂利をかみしめながらどうにか立ち上がった。
しかし、その頃にはもう、雌雄が決していた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
アルクェイドは黄金色の瞳を輝かせながら、新たな作戦を瞬時に練り直した。
(――三手で)
この“英霊”は危険すぎる。その上、今は
青い騎士が出現してから世界が砕けた――これが原因だ。
ならば、これを滅ぼせば良い。
いや、できることなら――
「――!」
青い騎士は息を止めたまま閃光の踏み込みで不可視の剣を叩き込んできた。
切られるままに任せる。
胴を横に切り裂かれ、臓物がまき散らされた。
騎士が目を見開く。真祖の姫は黄金色の瞳を楽しそうに細めながら躰を霧と化した。
刹那、《世界》が真祖の姫の空想を紡ぎ出した。
瞬時に出現したのは――四方向から取り囲む、四人のアルクェイド・ブリュンスタッド。
八つの黄金眼が輝く。
四つの爪撃。
「――!!」
騎士は右足を軸に、回転しながら、莫大な虹色の魔力を不可視の剣に注ぎ込んだ。
魔力が烈風を生む。
固体のごとき風の
だが、姫は四人ではなかった。
天井が砕ける。
高空に紡がれた五人目が超高速でまっすぐ落ちてきた。
両腕を交差し、隙間から黄金色の瞳を輝かせている。
姫は激突の瞬間、交差させていた両腕を広げるようにして、金剛石より固い爪により蒼い騎士を切り裂こうとしたのだ。
だが、騎士は倒れ込みながら、まるで最初から勘付いていたかのように神速の刃を絶妙なタイミングで真上に叩き込んだ。
不可視の剣が、交差する爪と激突する。
剣が砕けた。
同時に、荒れ狂う暴風が姫の腕を切り裂いた。
痛み分け。
いや――《白き姫》は会心の笑みを浮かべている。
――ドドドドドッ!
突如として騎士を取り囲むように床という床が下から打ち砕かれた。
何かが突き出してきたのだ。
騎士は飛び退こうとする。しかし、時すでに遅し。
「!?」
騎士の体に何十本もの鋼鉄の鎖が巻き付いていった。
「この程度で――!」
セイバーの躰を目視できるほどの虹色の魔力が包み込んだ。
力業だ。
爆発的な魔力の放出で鎖の拘束を解き放とうとしているのだ。
だが、その行動が《白き姫》にひとつの決断を促した。
五体のアルクェイド・ブリュンスタッドが一瞬にして濃霧へと変わる。濃霧は爆発的に拡散し、室内はおろか、廃墟を埋め尽くし、廃墟の外でどうにか起きあがったばかりの士郎すら巻き込んで――
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「まさか――!?」
シエルはザザザッと地面をえぐりながら急停止した。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「えっ――!?」
それは士郎の予測を遙かに超える現象だった。
彼は花畑に立っていた。
周囲には色とりどりの花々が、見渡す限りの平野に咲き乱れている。そればかりか、遙か彼方にはお伽噺にでも登場しそうな西洋風のお城が建っていた。そのさらに向こうには、星ひとつ
(……月?)
とても美しい満月が輝いてた。
――我が慈悲に涙せよ。
声が響いた。
――本来であれば即座に処断するところだが、そなたに尋ねたき事柄がある。もっとも、そなたが無闇に魔力を放出しなければ、コレを紡ぐことも適わなかったであろう。それゆえの慈悲である。その口で問いに答えることを許そう。
風が吹いた。
花びらが舞い上がる。
「んっ――」
士郎は瞬きをした――と、誰もいなかったはずの花園の一角にひとりの姫君が立っていた。
背になびく黄金色の髪。
月光に照らし出される純白のドレス。
――改めて歓迎しよう。ようこそ我が城――《
かつての姿を取り戻した《白き姫》。それもまた、大いなる【矛盾】だった。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.