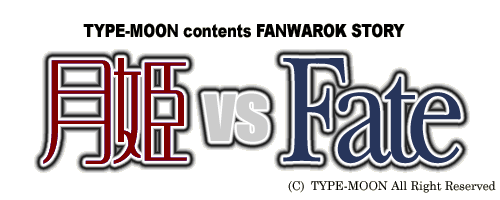
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[08]
-
3
……そうして、ひとつの夢が終わった。
セイバーは力尽きたかのように横たわり、脱力感に襲われた士郎も、そんな彼女に覆い被さっている。
セイバーは鎧こそ消しているが青いドレスを身につけたまま。
士郎もズボンをわずかにズリ降ろしただけ。
二人は結ばれるためだけに互いを求め、貪るように結び、欲するままに同時に達し……
「――――こほんっ」
ベッドの傍らにはライダーが立っていた。
「「うわっ!」」
抱きしめ合ったままゴロゴロと奥へと転がる士郎とセイバー。
ドンッと床へと落ちると同時に、白い閃光が放たれる。次の瞬間、完全武装のセイバーは、こちらも完全武装のライダーの首に無銘の名剣を突きつけていた。
「い、いつからそこに!?」
「『だめ、意識が、飛んで』というところからです」
「なっ……なっ……なっ…………」
耳まで真っ赤にしたセイバーはプルプルと震えだす。おかげでライダーの首筋にプツリと血の筋が生まれるが、ライダーは別段、気にした様子も無い。
「それにしても見事な
「ライダぁぁぁーっ!」
「ま、待てセイバー!」
慌てて士郎が背後からセイバーを羽交い締めにした。
「シロウ、離してください!
「そういう問題じゃないだろ!」
「いいえ、そういう問題です!」
「いや、だから、ライダーは味方なんだって!」
「問答無用!」
「士郎、目を」
ライダーは右手で、自分の顔を軽く撫でた。あわてて士郎はまぶたを強く閉ざす。途端、ライダーの目隠しが消え去った。
――ギンッ!
「き……貴様…………」
錯乱していたということもあり、セイバーの力は一気に衰えていた。それでも人並みに動けるのだから、なかなかの化け物ぶりである。
「……ここでの出来事は、後ほど、士郎も交え、ゆっくり話し合うことにしましょう。それよりも今は緊急事態です。まずは落ち着いて下さい。よろしいですか?」
よろしいもなにも、そう言われては落ち着くしかない。
渋々セイバーが頷くと、ライダーは
「士郎、もう大丈夫です。それにしても非常識な躰ですね」
「んっ? なにが?」
恐る恐る目を開けた士郎が尋ね返す。
「……いえ、その話も後ほど、ゆっくり」
そう告げたライダーは左拳を二人に差し出した。
「凛がお待ちです」
拳の中には、大振りな宝石が収まっていた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
――あーっ、あーっ、あーっ。衛宮くん、聞こえる?
「あぁ、聞こえるぞ。そっちは?」
ベッドの上にあぐらをかいた士郎は宝石に向かって尋ね返した。
――OK。じゃあ、
宝石から響いてくるのは新都にいる凛の声だ。どうやら留学中に遠隔会話の魔術――正確には宝石を振るわせることで“声”を交換する魔術――を習得したらしい。今だ携帯電話が“大きすぎる”ことを考えれば、実に簡単で便利な連絡手段だ。無線機で事足りるという話もあったりするが。
――まずセイバーのことだけど……セイバー、そこにいるんでしょ?
「はい」
彼女は士郎の傍ら、ベッドの上に正座している。すでにその顔からは不安の影は消え去り、照れや気恥ずかしさも感じられなかった。表情だけ見れば生真面目そのものの。士郎の記憶にある二年前のセイバーそのままだ。
「リン、最初に話しておきたいことがあります。実は――」
――あぁ、言わなくてもわかってる。複数の記憶があるってことでしょ? 当然よ。そもそも前の戦いで召喚された《英霊》、ひとりとして本当の意味で消滅していないもの。
「……はぁ?」と士郎。
――冬木の土地で行われる聖杯戦争、《根源の渦》にいたる歪みを人工的に生み出す大儀式だったってこと、覚えてるわよね? そりゃあ、アインツベルンが《
「いや、でも、《大聖杯》は壊れたし――」
――いいから聞くの!
「わかった。続けて」
――いい!? 《大聖杯》を閉ざしたのはイリヤ。でも《英霊》をため込んでたのは桜。おまけにあの時、《大聖杯》の中にいた《
「馬鹿で悪かったな」
――いいのよ。おかげで桜の中に《英霊》が残ったし。
沈黙。
「何が残ったって?」
――《英霊》よ。なんでか知らないけど、桜の《器》に残ってるのよ。今も《根源の渦》とつながってる理由、それならわかるでしょ?
「いや、でも――」
士郎はセイバーを見た。
「それだと
沈黙。
――ごめん。今、なんて言ったの?
「だから、セイバーは聖剣を持ってないんだ。そうだろ?」
「はい」
うなずき返したセイバーは、士郎が手にする宝石に目を向けた。
「私にも別の世界線の記憶があります。誓いを破った私をシロウに止めてもらえた記憶とは別の……シロウと共に英雄王と戦い、これを破り……あの丘に戻った記憶です」
その表情は辛そうにも見えるが、どことなく懐かしんでいるようにも見えた。
「私はベディヴィエールに命じ、“剣”を湖に捨てさせました。そのあと……おそらく私は死にました。次に覚えているのは、シロウが見知らぬ男性に襲われているところです。その時は、これが夢の続きなのだと……しかし世界が砕け、森で目を覚ましたあと、私は気絶していたシロウを近くにあった廃墟にかくまい、周囲を調べました。その時、“剣”がベディヴィエールのものになっていたことに気づきました。それから私はシロウにこのことを相談し、魔力の補充を受けました」
そこでようやくセイバーは口を閉ざした。
静寂が続く。
(……んっ?)
士郎は微妙にイヤな予感を覚えた。何か最後に不穏当な言葉が――
――早く言いなさいよ!
廃墟中がビリビリと震え、士郎の手から宝石が跳びはねていった。
――最悪じゃない! それってセイバーが“そう”だっていうことでしょ!? どうしろっていうのよ!
「と、遠坂!?」
耳がキーンと鳴り続けている。士郎だけでなく、セイバーやライダーも耳に両手をあて苦しんでいるようだ。
――無理を承知で聞くけど、あんた、セイバー殺せる!?
「な、なに言ってんだ!? せっかく戻ってきたんだぞ!?」
――そのセイバーが【矛盾】のひとつなのよ! いい!? 今、冬木市にいる人間は私たちと駅前で襲ってきた連中だけ! 駅前に二人! 円蔵山に二人! 真祖と《代行者》は行方不明だけど、絶対、どこかにいる! これがどういう状況かわかってる!?
「わかるわけないだろ!」
――歪んだ世界線が生まれたのよ! 閉じこめられたの、特殊な並行世界に!
「……なんでさ」
――ちょっと待って。私も落ち着くから。
シーツの上に落ちた宝石は、それから三秒ほど沈黙した。
――よしっ。
凛の声が流れる。
――あんたもありえない過去の記憶、持ってるわよね。それ、並行世界の記憶よ。でも、思い出せる記憶って、実際のものを含めて五種類ぐらいじゃない?
「えっ? まぁ……そういえばそうだな」
――難しい理屈は省くけど、これ、私たちの世界と共鳴しやすい世界線が全部で四種類しか無かったってことなの。四つじゃないわよ。あくまで基本が、私たちの世界線を含めて五軸あるってこと。そこから分岐する別の記憶もあるでしょ?
「んっ、まぁ、そうだけど……んっ? あれ?」
士郎は疑念を抱いた。
“ありえざる記憶”は、聖杯戦争が起きた二年前のあの時期のものしか……
――気がついた? 記憶の時期が限定されていること。
「まぁ……なんとなく」
――ポイントはふたつ。多次元的な現象が起きたけど、私たちに対する影響は記憶に関するものだけ。しかも、その記憶は二年前の聖杯戦争に限られている。だから死人は蘇らないし、あんたの躰も素体のまま――それにしても随分馴染んだんじゃない? 真祖の攻撃、あんなにしのげるなんて。
「いや、あれは守りに徹しただけで……」
――アーチャーのおかげ?
「……多分」
士郎は自身の左腕をギュッと掴んだ。
「それより、閉じこめられたってどういうことだ?」
――あぁ、それね。とりあえず、記憶の多重化は《世界》を壊すほどの【矛盾】にならない。言ってしまえば別の人間の記憶を移植されたぐらいのことでしかないもの。でも、《世界》は大きな【矛盾】を抱えると、それを修正しようとするわ。
「【矛盾】を修正?」
――あんたが不完全な投影しかできなった時、投影物って放っておくと消えちゃうでしょ? それのことよ。
「はぁ……」
わかったような、わからないような。
――小は魔術から大は超越種の実在まで、全ての“神秘”は【矛盾】を修正しようとする《世界》の修正力を、何らかの代償で騙しているわ。魔術の場合は魔力や痛み、超越種の場合は反転衝動。これも等価交換の原則の一種――ううん、より本質的な部分と言うべきね。
「つまり……代償を支払わない神秘が起きたせいで妙なことに?」
――そういうこと。本来、そういう神秘は“魔法”だけなの。もっとも、“魔法”にしたって《世界》ではなく《大世界》の神秘であって、その範囲での等価交換の原則は守られてるから本当の意味で【矛盾】しているとは言えないのよ。
「へぇ……」
―― ………………。
「……遠坂?」
――ずいぶん味気ない反応ね。
「えっ?」
――私、“魔法”の秘密を打ち明けたつもりなんだけど?
「いや、今は閉じこめられたこととか、セイバーのこととか……重要なのはそっちだろ?」
――はいはい、あんたがそういうやつだってこと、すっかり忘れてたわ。
宝石が溜息をついた。
馬鹿にされた気がして少しムッとしたが、士郎は黙って凛の言葉を待った。
――じゃあ、状況を整理するわよ。
改めて凛は語りだす。
――いち、
「よくわからないけど、とにかくわかった」
――よろしい。
凛は満足げに言葉を続けた。
――に、記憶の重複期間からして二年前の聖杯戦争が【矛盾】の根源に関係している。
さん、例の真祖たちも巻き込まれている以上、【矛盾】の根源に連中も関係している。
よん、【矛盾】が解消されるまで私たちは異相世界の……異次元の冬木市に隔離された。
ご、異次元の冬木市は、私たちの存在概念を切り離す時に張り付いてきたオマケみたいなものだから、ものすごく不安定で、いずれ限界が訪れると木っ端微塵に崩壊する。
「おい、それって――」
――ろく、制限時間はおそらく残り十時間前後。それまでに【矛盾】の解消、具体的には【矛盾】を内包する人物を消去しないと、私たちは世界と一緒に消滅する。エーテルの痕跡すら残さず。きれいさっぱりとね。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「――つまり十時間以内にどうにかしないと終わりということですね?」
シエルはコンパスを取り出しながら溜息混じりに尋ね返した。
「そういうことになるかな」
一方、すぐそばに着地したアルクェイドは、ノンビリと濃霧に閉ざされた樹海を眺めている。
共に全速力で走れば時速百キロを越える化け物だが、ここは土地勘も無い上に濃霧に包まれている樹海の中だ。おまけに方向感覚を狂わせる魔力が土地に強く根付いている。そこで二人は、シエルが持つ特殊なコンパスで方角を確認しながら森を駆け抜けているところだった。
「それよりシエル、本当にこの方角でいいわけ?」
「当たり前です」
彼女は左手に持つコンパスに目を落とした。形状こそ普通のコンパスだが、針に乗っているのは永久磁石ではない。“蛇”がシエルに残した魔術知識の結晶、特殊な探知用魔術道具――遠野志貴にのみ反応する赤い魔術の針だ。
原材料は志貴の血液。仕入れ先は割烹着の悪魔。代価として大枚をはたくことになったが、金で解決できるならたやすいもの。それにしても、あの悪魔が金銭を要求してくるとは意外だった。
(んっ? そういえば…………)
そもそもこれを作るキッカケは、
――いずれ私たちが知らない間に志貴さんが連れて行かれるかもしれませんね。いざという時、探し出す手段とかあったら楽かもしれませんけど。
という悪魔の囁きだった気が……
(謀られたのかも……)
いや、金で解決できたのだ。それで良しとしよう。
どうせ言われなくてもいずれ作った道具だ。それに充分な血液を確保できたおかげで、志貴のいる方向を突き止めるばかりか、地図で探せば一発的中できるというダウジング能力まで付与できた。なかなかの傑作だ。
しかし、今回の追跡劇では冬木駅に到着したあとに活躍した程度である。結局、目的地を突き止めたのは翡翠だった。ただでさえ少ない志貴の荷物のうち、少量の着替えが無くなっていたことと、部屋に残された冬木市の観光案内パンフレットとがその決め手だったのだ。
(……んっ?)
そういえば自分たちの切符の手配は琥珀が仕切っていた。
さらにいえば、少し前、しきりに地方の花見処を口にしていたのも……
「シエルぅ、もしかして方角違うとかぁ?」
「……アルクェイド、どうして花見の場所に冬木市を?」
「にゃっ? どうしてって……観光客が少ない穴場なんでしょ? 琥珀にそう聞いたけど」
恐るべし、割烹着の悪魔。
「でもまぁ、この様子だと誘われただけかも」
アルクェイドは髪をかきあげながら吐息を漏らした。
「誘われた?」
“
「そっ。誘われたの。運命の糸に」
「運命? ここにくることが必然だったとでも?」
「どうかな。そんな気もするなーって」
「……根拠は?」
「う〜ん……とりあえず前から興味はあったのよ。だってさ、アオザキが管理してない一等霊地でしょ? 純粋にどんなところかなーって思ったわけ」
「根拠になってません」
「なってるじゃない。私が気にかけていた場所に、絶妙なタイミングで行くように促す出来事が起きた――そこに意味があるのは当然よ」
アルクェイドは笑った。
こういう時、シエルは背筋に冷たいものを感じる。
今や悪友めいた付き合いになっているが、目の前にいる女性は正真正銘の“世界の抑止力”、《白き姫》アルクェイド・ブリュンスタッドだ。それを考えれば、二年前の事件や志貴との出会いなどが全て偶然だったとは言い切れない。
遠野志貴は《世界》を殺せる人間だ。実際、限定された空間とはいえ、彼は《世界》そのものを殺したことがある。これが意味することはひとつ――彼は《世界の敵》になりえる存在、ということだ。
アルクェイドが志貴の恋人になりえている理由も、元を正せばそれゆえのはずである。
あくまでシエルの予想だが――“その時”になれば、アルクェイドは吸血衝動を越える衝動に突き動かされ、間違いなく遠野志貴を襲うはずだ。それがダメでも、《白き姫》の死はそのまま《朱き月》の再臨を意味する。《朱き月》でもダメなら、《世界》の死は確定したも同然。それ以上を考える必要は無い……
だからこそ、《白き姫》のロマンスは許されている。
理由は問わない。《世界の敵》候補のそばに居られるのなら、《世界》は何も言わない。
いずれ殺し合うからこそ、愛し合うことが許されている。
哀しすぎる恋だ。
それでは、あまりにも二人が…………
(――でも!)
だからこそ、譲るわけにはいかない。ここで譲ってしまっては悲恋を、《世界》の無慈悲を認めることになる。だから決して、譲るわけにはいかない。なにがあろうと自ら退いてはならない。
「……なに気合いいれてんの?」
アルクェイドが呆れ顔で尋ねた。
だがシエルはコンパスをしまいつつ、平静そのもの表情で彼女に顔を向けた。
「なんでもありません。さっさと【矛盾】を解決して、志貴くんとお花見に行く決意を固めただけです」
「あーっ、邪魔邪魔。志貴は私と二人っきりでお花見するんだから」
「却下します。どこぞのアーパー吸血猫と一緒では志貴くんも楽しめるわけがありません」
「どこぞのカレーの年増と一緒の方が楽しめないに決まってるじゃない」
「……アルクェイド、桜がなぜキレイか知ってますか?」
「ヨコミゾセイシなんて年増の証拠ね」
ドラゴンとタイガーがサンダーをバックにゴワーンと鳴りそうな空気。
「話を戻しましょう」と、シエル。
「そうね」と、アルクェイド。
「根本的な質問です。【矛盾】を解消するのは良いとして、具体的にはどうすれば良いと?」
「【矛盾】を消す」
「答えてなってません」
「因果は“ヒト”に結びつきやすいでしょ。だから、【矛盾】を内包した“ヒト”を見つけ出して【矛盾】ごと消す。ほら、答えてるじゃない」
「つまり“蛇”を探し出して消す、と?」
「それもあるけど――異相世界が生まれる直前、青い騎士の《英霊》が現れたでしょ。あれも【矛盾】と見るのが妥当なはずよ」
「彼らもここに?」
「多分ね。もっとも、向こうにすれば私が【矛盾】の一端に見えるんじゃないかな。あとシエルと妹も危ないわね」
「根拠は?」
「決まってるじゃない」
アルクェイドは不敵な笑みを浮かべた。
「私たちが――」
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「――《世界》に容認された【矛盾】だから、か」
士郎はシーツの上の宝石を見据えたまま考え込んだ。
――そうよ。だから第二魔法の影響でどうなってるか、わかったものじゃないわ。できれば無視したいけど、最悪、戦うことも考えてといてね。
正直、あまり考えたくない。
特に、あの白い脅威と黒髪の“死”は、セイバーがいても勝てるかどうかわからない相手だ。そもそも遠目に見た限り、あの二人は存在こそ特殊だが、ごくごく普通の恋人のように思えた。そんな二人をわざわざ敵に回すのは……
――でも、当面は無視して大丈夫。【矛盾】の根源、《大聖杯》があった洞窟にいるから。
宝石越しに凛の声が響いた。
――連絡がくるまでイロイロやってたのよ。そうしたら、柳洞寺から妙な魔力が感じられたってわけ。移動する気配も無いから、最初にここを潰すのが妥当なはずよ。これで全部解決するなら結果オーライ。ダメならダメで真祖と戦う。そんなところね。
「あの黒髪は?」
――死神みたいなヤツのこと? 無視、無視。【矛盾】を内包できるような器じゃないもの。あっ、そうそう。セイバーも【矛盾】の一端なのは間違いないけど、セイバーはサーヴァントだし、こっちには桜もいるわ。何か抜け道があるかもしれないから、合流までに考えておくわね。あぁ、そうだ。合流先は深山中央の交差点でいい?
「わかった。すぐ移動する」
――ライダーは真祖と《代行者》を探して。見つけたら宝石で私に報告。
「わかりました。ところでサクラはどうしていますか?」
――ストライキ中よ。
「やはり」
ライダーは士郎に顔を向けた。
しばらく「?」と首を捻る士郎だったが、次第に脂汗が流れ、「まさか……」という表情に変わっていく。
――どうでもいいけど……衛宮くん。自分の魔力の流れぐらい把握しなさいよ。魔力供給なんて一発でバレるに決まってるじゃない。
「いっ――!?」
――以上、通信終わり。
その言葉を最後に宝石は振動をとめた。
士郎は固まったまま黙り込んでしまう。隣のセイバーは「むむむっ」と顔をしかめ――
「シロウ!」
「な、なんだセイバー!?」
「サクラとはどのような関係なのですか!? 正直に白状してください! それとも言えない間柄なのですか!?」
「いっ!? あっ、いや、それは、だな、つまり、その――」
「ご愁傷様です」
ライダーは一礼してから窓に向かった。
「ラ、ライダぁぁぁ!」
「シロウ! まさかライダーとも!?」
「いや、違う! だから、その、確かに桜は恋人というか、そういう関係だけど――」
「私を弄んだのですね!?」
「違う! それだけは絶対に違う!」
士郎はセイバーの両肩を掴んだ。
「本気だ! 本気でセイバーのことも愛してる!」
静寂。
窓辺で硬直しているライダー。まったく同時にボッと赤面する士郎とセイバー。
セイバーは顔をうつむかせ、
「……信じても……いいのですね?」
「う、うん……」
士郎はどうにか答えにもならない答えを返した。
再び廃墟が静まりかえる。
「……わかりました」
セイバーは正座したまま、士郎から少しばかり離れ――何を思ったのか、三つ指をつき、深々と頭を下げた。
「ふつつか者ですが、よろしくお願いします」
「……はい?」
「そもそもサーヴァントの身の上で正妻の座を求めるなど、過ぎた望みでした」
「セ、セイバー?」
「それにサクラの女主人としての力量は間違いなく私より上です」
「い、いや、だから……」
「かくなる上は第二夫人としてサクラを助け、衛宮の血を後世に残すべく、精一杯はげみたいと存じ上げます!」
「存じ上げるな!」
「どうしてですか!?」
「どうしてって――」
「シロウ!」
セイバーは一瞬で士郎の胸元に迫った。おそるべき速さだ。
「シロウは私のこと嫌いですか!?」
「そ、そんなわけないだろ!」
「でしたら!」
彼女はキュッと、士郎の胸元をつかんだ。
「私は……二人目でいいです…………」
ぐはっ。
「……士郎」
見ると窓辺に残っていたライダーが振り返っていた。
「私は愛人で我慢します。では」
フワッとそよ風を残し、姿を消すライダー。
またまた静寂の時が流れる。
「シロウ! やっぱりライダーとはそういう関係だったのですね!?」
「違う! それだけは断じて違う! ライダーとはまだなにも!」
「“まだ”!?」
「……あっ」
「シロ――――――――――――――――――――――ウ!」
セイバーが落ち着いたのは、彼女が登場した淫夢について白状したあとのことだった。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.