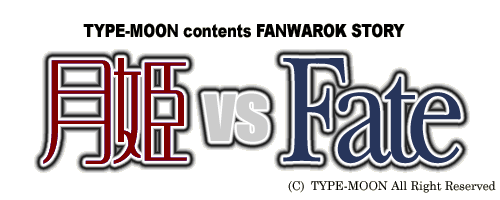
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[07]
-
2
「私は……私なのですか……?」
セイバーは震えていた。
(反則だろ……)
士郎は素朴な感慨を抱いた。
この二年、彼を支えてくれたのは間桐桜という別の少女だ。毎夜のように躰を重ねているのもそう。ただ、何度言っても辞めてくれないライダーの淫夢のせいで微妙に困った問題も起こっている。
(そういえば……)
士郎はふと、懐かしい記憶を思い出した。彼の養父、衛宮切嗣に関するものだ。
記憶の中の自分は、切嗣と縁側に並んで座っていた。
見上げるのは丸まるとした満月。
――いいか、士郎。
士郎の“正義の味方”は笑顔で義理の息子にこう語りかけた。
――男は四、五人の女を同時に愛してこそ一人前だ。
(おやじぃぃぃ!)
衛宮切嗣――彼は自称“女性の味方”だった。
「違う! 絶対に違う!」
士郎は断言した。
セイバーが驚いているが、士郎にしてみればそれどころではない。
自分はそんな無節操ではない。確かに夢の中では無節操だが、それはあくまで夢の話だ。現実では桜一筋、ライダーに手を出したこともない。いや、たまに眼鏡越しに見つめてくる瞳にクラクラすることもあるが、それはあくまでライダーの容姿が神がかっているからであり、決して誘惑に弱いとか、押しに弱いとか、理性がふっとぶとオオカミになるとか、そういうところがあるからでなく……
「シロウ……」
見るとセイバーはうつむき加減で見上げてきていた。まるで迷子になった幼子のような涙目で。
「……私は……王では……ないのですか?」
ぐはっ。
士郎は心象世界で吐血した。
五軸の記憶がグルグルと脳裏を巡る。特に、セイバーとあーんなことになってしまった記憶が――
「セイバー!」
「は、はい!」
士郎はガッとセイバーの両肩を掴んだ。
セイバーは突然のことで、躰を強ばらせながらピンッと背筋を伸ばしている。
「セイバーはセイバーだろ!? 王じゃなくても、セイバーはセイバーで……だから……そう! もう、いいんだ! 聖杯とか何だとか、そういうことはもういいんだって!」
「ですがシロウ! それではどうして私がここにいるのか――」
「どうでもいいじゃないか!」
士郎は叫んだ。
「そんなこと、もう、どうでもいいじゃないか……俺がいて、桜もいて、凛もいて……そうだ、ライダーもいるんだ。桜の魔力で、聖杯の力が無くてもここに居続けられるんだ。だからセイバーだって……」
「ライダーも……?」
「あぁ、だからセイバーも……」
「…………」
「…………」
二人は黙り込み、互いの瞳を見つめあった。
記憶とは曖昧なものである。それも二年前の記憶ともなれば、明確に思い出せるものは断片程度というのが普通だ。しかも今の士郎には五軸の世界線の記憶がない交ぜになって存在している。彼の中では“セイバーを自らの手にかけた記憶”と“セイバーと結ばれた記憶”が等価なものとして存在しているのだ。
この混乱はセイバーの方がより強く表れていた。なにしろ彼女にとって二年前とは“昨日”の出来事なのだ。黄金の別離を迎えた記憶も、凛をマスターとしつつ残った記憶も、あの丘へと戻った記憶も、士郎に殺してもらうことで誓いを破らずに済んだ記憶も、逆に誓いを破って殺してしまった記憶も……全てを明確に思い出せるがゆえに、彼女は士郎以上に混乱していた。
だからだろう。
二人は顔は自然と近づき、互いの呼吸を肌で感じ取れると…………
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「むっ」
桜は顔をしかめた。
「なにか見つけた?」
少し離れた場所に立つ凛が振り返ってきた。
「士郎さんが」
「……そういうこと」
どうせ相手はセイバーだろう――そう察しを付けながら凛は深々と溜息をついた。
性交渉という交換魔術は互いを結ぶ擬似的な魔術回路を作り上げることを目的としている。正確には男性の陽性と女性の陰性を環流させることを目的とするのだが、絶頂のタイミングを合わせる程度であれば、魔力のパイプを作るだけにとどまってしまう。こうして生まれたパイプは、水が高きから低きに流れるように、一方から一方へと魔力が流れ込む程度の作用しか示さない。ただ、ほんの少し細工を施すと、一方向にのみ魔力を流すことができる。これが吸精と呼ばれる外法の正体だ。
いずれにせよ、毎夜のように肌を重ねている桜と士郎の間には、魔力が流れるパイプが今現在も存在している。桜は吸精の業を身につけているが、当然、そんなものを使っているはずがない。つまり、今は純粋な魔力量の問題により、桜を供給側、士郎を需要側とするレイラインが生まれているだけだと見ることができる。
これが何を意味するかといえば――
(浮気は全部バレバレなのに)
あの“正義の味方”は“性戯の味方”でもあるらしい。
「とりあえず衛宮くんのことはほっときなさい。セイバーが一緒なら安心だし」
「……姉さん?」
「なに?」
見ると桜はすねるような表情のまま、凛のことを見上げてきていた。
「姉さんは士郎さんのこと、どう思ってるんですか?」
以前には見られなかった表情だ。留学する以前、桜は凛に対する嫉妬すら大きな罪悪に感じるような状態だったのだが、どうやら可愛らしい嫉妬を発露させる程度には“自分勝手さ”を取り戻せたらしい。
良い兆候だ。
独善性は人間が人間らしくあるために必要な要素のひとつだ。強すぎるのは問題だが、まったく無いのも問題である。それだけに姉としては、こうした桜の表情は実に微笑ましい。
「魔術師としては興味あるわよ。あんな珍品、滅多にいないし」
「……異性としては?」
「あるわよ。当然」
凛は眼下を眺めながら、平然ととんでもないことを口にしていた。
ここは新都オフィス街。凛と桜、さらにライダーが転移した場所は、その裏路地にあたる場所だった。凛とライダーには縁の無い場所だったが、桜にはそうでもないらしい。青ざめた表情から凛はそうと察していた。
――あのビルの屋上に登るわよ。
急ぎ、場所を変えたのはそのせいだ。
向かう場所は、別の世界線でセイバーとライダーが死闘をくりひろげたビルの屋上。逃げ道を考えれば愚策としかいえないが、いざという時、ライダーに全力で戦ってもらえる場所といえば、高層ビルの屋上が最適だったのだ。他にも、魔術で情報を集めるには街を一望できる場所が好ましいということもある。
こうしてライダーぶ担がれた凛と桜は屋上に急行。その後、危険が無いと判断した凛は、桜の了承を得てライダーに士郎を探すよう命じた。今頃ライダーは町中を超高速で駆け抜けつつ、セイバーとちちくりあっている士郎の姿を探しているはずだ。
(……あっ、やってる最中なら屋内にいるってことよね。家に帰ってたりして)
凛は頬にひっついた髪を後ろに流した。
と、桜が祈るように胸元で指を絡め、涙目になりつつこちらを見ていることに気がつく。
(もう……)
凛は今日だけで何度目になるかわからない溜息をついた。
「桜にもあるんでしょ、他の世界線の記憶」
ちらりと見ると、桜はコクリと頷き返した。
「だったらわかる……わけないか」
凛は再び溜息をついた。
「とにかく、これだけは信じなさい」
凛は妹を見た。
「今の私にとって一番イヤなことは――桜に嫌われることよ」
桜は目を見開いた。それから顔を伏せ、風に流される髪を抑えつつ、遙か彼方に視線を走らせた。
「私、姉さんのこと、大好きです」
「衛宮くんの次に、でしょ?」
凛は意地の悪いの笑みを浮かべ、妹と共に冬木の街並みを眺めるのだった。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
眺めたところで、誰かいるわけでもない。あれほど倒れていた通行人すら、今や影も形も無くなっている。
(……どういうこと?)
秋葉は真紅の髪をなびかせながら、駅前広場の中央で改めてグルリと周囲を見渡した。
突然の頭痛と“ありえざる過去”の記憶の奔流。それだけでも破格の異変というべきだが、不意に七色の輝きが世界を見たし、次の瞬間には駅前広場の中央に倒れていたのである。
しかも志貴の姿も無ければアルクェイド、シエルの姿もない。
唯一、一緒にいたのは――
「秋葉さまぁ、やっぱり誰もいないみたいですよぉ」
カラコロと外履きの音を響かせながら走ってくるのは、凧のように袖を横に広げつつ走る遠野家の使用人――
「お店の中も無人なんです。それより、まだ高ぶりは収まりませんか?」
「……ねぇ、琥珀」
「はい、なんです?」
「……復讐は、もう、いいの?」
「はい」
即答だ。表情も笑顔のまま、なにひとつ変わらない。
それだけに痛々しい。秋葉はグッと歯を食いしばり、顔を背けた。
「本当に……それでいいの?」
「秋葉さまには感謝しています。槙久様から私と翡翠ちゃんを救ってくださったことも、槙久様の殺害を見逃して下さったことも、四季様を解き放ったことすら見逃してくださったことも」
「兄さんが生きてたからよ」
もし志貴が死んでいたら決して琥珀を許さなかっただろう。
「本当ですか?」
琥珀はクスクスと笑いながら尋ね返してきた。
(……これだから琥珀は)
答えなど決まっている――“嘘”、だ。
結局、なにをやろうと秋葉は琥珀を許してしまうのだ。もちろん、志貴が死ねば、激昂した自分は琥珀を殺していたはずだ。しかし、恨みを抱くとは思えない。
自分は遠野家の当主。琥珀には遠野家に復讐する理由と権利がある。それがわかっているからこそ……
「秋葉さま、もう、よろしいと思いますよ」
顔を向けると、琥珀は変わらぬ笑みを浮かべていた。
「全部、終わったことですから」
「……そう」
秋葉は髪をかきあげた。朱色だった髪は黒に戻っている。血の
「それに志貴さんが翡翠ちゃんに手を出してくれるまで――」
「――琥珀、今、何か言わなかった?」
「秋葉さまと志貴さん、法律上は兄妹ですし、犯罪ですよねぇということですか?」
「!?」
秋葉は怯んだ。
まさか琥珀にも“ありえざる過去”の記憶が? だとすると――!!
「こ、琥珀!?」
「お屋敷の離れは危険ですよぉ♪ いつ壊れるともしれませんしぃ♪」
カランコロンと外履きを鳴らしながら琥珀は近くのコンビニへと向かった。
(か、勝てない……)
心の底からそう思う秋葉だった。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「降参。まいった。だから、起こしてくれないかな」
志貴は両手をあげていた。
ここは遠野の屋敷、志貴の自室だ。ベッドの上に寝そべる志貴のお腹の上には小柄な女の子がペタンと座り込んでいる。黒いコートを着込んだ紫髪の女の子だ。大振りなリボンが耳のようでもあり、クリッとした瞳は猫の瞳孔そのものだった。
名はレン。とある事情で志貴が
「落ち着いたら、な」
苦笑まじりに志貴が告げると、レンは無言で右手を差し出してきた。小指がたっている。どうやら指切りで約束したいらしい。
「約束する」
志貴は指切りで応えた。
レンの目元が少しだけ和らぐ。あまり感情を表に出さない少女だが、実は単に表し方を知らないだけにすぎない。そうと判って接し続けると、レンが実に多感な女の子であることに気づかされる。
「よーし、いい子だ」
志貴はあいている左手で彼女の頭をクシャクシャと撫でた。
目を細めるところは猫そのもの。ふつふつと保護欲がかきたてられる反応である。
それはともかく。
「――さま、志貴さま。起きて下さい。志貴さま」
スッと意識が沈み込んだかと思うと、すぐさま志貴の意識は明瞭さを取り戻していった。
「おはよう、翡翠」
「……おはようございます」
傍らに正座していた翡翠は安堵の笑みをこぼしていた。
口元がわずかに緩むだけの笑みだが、二年近く一緒にいたおかげで彼女の表情の変化は理解できるようになっている。だからこそ、レンの微妙な変化も理解できるのかもしれない。
本質的な部分で翡翠とレンの反応はまったくといっていいほど同じなのだ。
いや、より正確には琥珀やアルクェイド、秋葉やシエルも……
顔は口以上に雄弁だ、というだけのことだろうか。
「さて……っと」
埃を払いながら立ち上がった志貴は、とりあえず周囲を見回してみた。
「どこなんだ、ここ」
どうやら斜面に生える雑木林の中らしい。耳を澄ませば小川のせせらぎと木々のざわめきが聞こえてくる。自動車が走り抜ける都会の喧噪はどこからも聞こえてこない。都市部の郊外なのだろうか。それにしても、わけのわからない出来事が連続しすぎている。
「おそらく柳洞寺がある円蔵山だと思われます」
翡翠も立ち上がり、パタパタと服についた埃や汚れを払い出した。
「柳洞寺?」
「駅前に観光案内のパネルがありました。室町時代に
「へぇ……」
振り返ると、翡翠はレンを抱き上げていた。
普段のレンは黒い仔猫の姿をしている。一応、人化の魔術を教わっているという話だが、魔力が浪費されるので、よほどのことが無い限り猫のままでいることが多い。
「レン、アルクの居場所とか、何か感じるかい?」
仔猫は首を横にふった。
「そうか……」
どうしたものか――と志貴は考え込んだ。
正直、何が何やらさっぱりわからない。もちろん超常的な異変が起きたことぐらいは理解できる。だが、わかることといえばそれぐらいだ。せめて
「合流しようにも……う〜ん」
志貴はガリガリと頭をかくことしかできなかった。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.