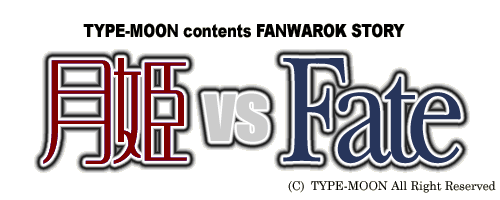
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[04]
-
4
(あれって、噂の天才魔術師……?)
秋葉はさらに目を細め、一瞬だけこちらを見据えていた少女の姿をより明確に捉えようとしていた。
彼女は鬼種の名家、“遠野家”の最期の一人にして現当主だ。
志貴は退魔を生業とする異能の一族、絶えたとされている“七夜家”の最期の生き残りである。ゆえに二人は血がつながっていない。しかし、戸籍上どころかその筋においても志貴は“遠野の血が薄い実の兄”として知られている……
いや、今はその話は横に置くとしよう。
重要なのは、鬼や異能者や魔術師が跳梁跋扈する日本の夜の世界において、遠野秋葉という少女が決して軽いとはいえないポジションに立っているという事実だ。
ゆえに彼女の耳にも遠坂凛という天才魔術師の噂は届いていた。
曰く――二十歳にして《協会》屈指の魔力を秘めた天才。
曰く――最も“魔法”に近い存在。
曰く――五大元素の全てに通じる大魔術師。
はっきりいって眉唾だ。日本人は海外で活躍する同胞を過度に賞賛する傾向がある。これらの噂も、そうした類のものに違いない。特に“魔法”に関する下りなど、数名しかいない“魔法使い”のうち、二名が日本人なら――という希望が生み出した妄想の産物のはずだ。少なくとも秋葉はそう思っている。だが、そう妄想させるだけの実力を、遠坂の当主が持ち合わせていることは事実だろうとも考えていた。
そもそも遠坂家は、異能を持って名を成している三家――かつては四家――ほどでは無いにしても、それに次ぐといわれる伝統ある名家のひとつだ。同家が管理する冬木の土地は日本屈指の一等霊地としても名が知られている。また、そこで古くから魔術に絡む特殊な大儀式が行われているという話も秋葉は耳にしていた。それが聖杯戦争と呼ばれるものだとは知らなかったが、やはり、並大抵の家柄ではないらしい。
そんな遠坂家の現当主にして名高き天才魔術師が、管理地である冬木市にいる。
おかしい。
噂では《魔術協会》の総本山、《時計塔》があるロンドンに留学中のはずだ。
帰省中なのか?
いや、そうだとしてもタイミングが良すぎる。
しかも天才魔術師の傍らに立っている紫髪の美女――秋葉もそれは素直に認めた――は、目にするだけで不快なざわめきを感じずにいられない“モノ”だった。
同類に対するシンパシーを感じる部分もある。
だがそれ以上に、我が身に対する危険を感じずにいられなかった。
あれは、危ない。
敵だ。
遠野秋葉という存在にとって、あの紫髪の美女は絶対的な天敵と呼ぶべき――
異変が起きたのは、まさにその時だった。
「――――――――――――――――!」
瞬間、彼女は何かを叫んだ。
秋葉だけではない。アルクェイドも、シエルも、後ろにいる琥珀や翡翠も何かを叫び、苦しみ、もがいていた。そうであると認識できたが、具体的にどう苦しんでいたかまでは理解できない。理解する余裕が無い。
(――――!?)
秋葉は“体験”した。
それも、命より大切な兄と戦う“経験”を。
――ダメ! イヤッ!
彼女は叫んだ。だが、その“経験”はすでに起きた過去の出来事。秋葉は鬼種としての力を用い、あろうことか、大切な兄を殺害していた。
悲鳴をあげた。
これ以上ないくらいの悲鳴を張り上げた。
それで終わりではない。
よく似た別のシチュエーションで、秋葉はまたも兄を殺していた。
それでも終わらない。
秋葉は様々な“過去”を追体験していた。
枝葉を除くと数は全部で九軸。不思議なもので、いずれも二年前の“あの時期”にまつわる過去ばかりだ。しかも、実際の過去と良く似ていながら、兄の隣にいるのがカレー好きの《代行者》であるという過去も存在している。そればかりか、九軸の過去の中には魅惑的なものまであった。
中でも琥珀に騙され、殺される過去には耐え難い魅力があった。
そうなるべき罪が自分と遠野家にはある――それを知っているからこそ、その過去は自らの破滅を意味しながら、甘美な夢であるかのように思えて仕方がなかった。
一方、困り果てるような過去もあった。
自分と兄が結ばれた過去だ。あまりにも都合が良すぎる過去である。ただ、そこで経験した破瓜の痛みは決して忘れたくないとさえ秋葉は感じた。どうせ自分は人並みの恋などできない身の上。ならば、たとえこの追体験が夢であろうと、初めてを捧げた相手が兄と慕う男性であったと……
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「うっ……」
外では士郎、桜、凛、ライダーが同様に苦しんでいた。
士郎たちの“過去”は枝葉を除くと全部で五軸あった。いずれも聖杯戦争にまつわる様々な顛末だ。その中では士郎がセイバーと結ばれる過去、凛と結ばれる過去、彼が死に残された桜が衛宮の家を守り続ける過去――ありえたかもしれない様々な過去が存在していた。
(――第二魔法!?)
最初に真相に気づいたのは凛だった。
彼女は無意識的に、《
(――多重現実――世界線――基点――蛇?)
理解の限界を超えている。
ただ、現象そのものは把握できた。なんらかの理由で特定の事象を基点に、起こりえた可能性の全てを追体験させられているのだ。通常であれば脳が悲鳴をあげるどころか全神経が焼き切れるほどの圧倒的な情報量である。だが、追体験しているのは、二年前の“あの事件”の前後のみである。おかげで情報量はそれほど多くない。
(みんなは……)
周囲の一般人は軒並み気絶している。情報過多による神経の損壊を、気絶という断絶によって回避したらしい。
一方、士郎、桜、ライダーは苦しみこそすれ、自分同様、意識を保っている。いずれも、この程度の情報量なら軽々と処理できる脳神経を持っている証左だ。
(当然よね)
彼女は少しだけ、そのことを誇らしく思った。
だが同時に、
(うわっ――)
凛は苦しみながらも赤面してしまった。
セイバーに魔力を注ぎ込むため、士郎と彼女の性交に手を貸した世界線があった。
士郎に魔力を移すという名目で、あろうことか躰を許してしまった世界線もあった。
そういう展開もありえた――凛は嬉しさと悔しさがごちゃまぜになるという、複雑な気分すら味わっていた。
(でも――)
彼女は誇れるものを見つけた。
それは桜が間桐家から解放され、士郎も生きている世界線が、今、自分のいる世界線しかないという事実だ。それどころか《大聖杯》を壊し、冬木の地における聖杯戦争を本当の意味で終わらせたのは、この世界線ただひとつだった。
自分たちは、最も良い結末を迎えた。
(これで良しとしなきゃ)
凛は自らに言い聞かせると、余計な感傷や推察は全て横に置くことにした。
今はなにより、この異変に対処しなければならない。
第二魔法に類するのは確実だ。しかし、実際の現象は第二魔法の本質から大きく外れている。いったいどうして、突如としてこんなことが起こったのか。その理由を探らなければ――
――ガシャーン!
窓硝子が壊れる音が響いた。
凛は顔をあげ、音の出所を見た。
広場中に倒れる気絶した一般人たち。その上を、ファーストフード店の二階の窓を中からぶち破った何かが、こちらに向け、飛び込んできている。
(……えっ?)
凛の目には、それが朱色の月に見えた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
アルクェイドは決して見たくないものを見てしまった。
吸血衝動に敗れ去った自分。
遠野志貴を殺してしまった自分。
いや、この二つは仕方がない。今は平穏無事だが、最初のひとつはすでに覚悟を固めている。そもそも吸血衝動とは、不老不死を体現しながら吸血種が衰退するしかなかった、最大にして唯一の理由なのだ。今更自分だけ例外だと考えるほど愚かな彼女ではない。
同様に、志貴を殺した記憶についても、それほど大きな衝撃にはならなかった。以前から「自分は、いずれ最愛のヒトを殺す」という確信めいた予感を抱いているのだ。少なくとも、自分はもともと、そういう存在であることをアルクェイドは自覚していた。もっとも、その時には一緒に“自分”も壊してしまうだろうことを彼女は覚悟している……
いずれにせよ、それらは未来の話だ。その時はその時。先々のことに頭を悩ませるなど、無限の時を生きるアルクェイドにとっては、今日の晩ご飯を悩むぐらいの意味合いしかない。
だが、真祖の姫は別のことで激昂していた。
志貴と出会わない記憶――それは、今の彼女にあってはならない世界線だった。
(どうして――!?)
“魔王”を殺すための兵器として生み出された自分。
真祖殺しの真祖として処刑の時のみ目覚めさせられた自分。
空を見上げることが安らぎであり、道を歩くことが楽しみであり、何かを食べることが娯楽であり、笑えることが幸せであると知らなかった自分――いや、その全ては二年前のあの時から彼女の中に生まれた“アルク”という心だ。それは日に日に彼女の中で大きく成長している。同時に、反発するように反転衝動も高まっている。
かつては七割の力で衝動を抑えていた。
一年前は八割。
今は九割の力を衝動の抑制に費やしている。
それでも彼女は“アルク”という自分を愛おしく思った。
自分を“アルク”と呼んでくれる人の笑顔と、その笑顔に笑い返せる自分を失いたくないと思っていた。
そのためなら、なんでもやる。
自分が“アルク”で居続けられるなら《世界》を敵に回してもかまわない。
だからこそ。
それゆえに。
(!!!!!!!!!!!!)
その記憶――彼女を“アルク”と呼んでくれる少年と出会わなかった世界線の記憶――は、アルクェイドの心を激しく揺さぶった。
(あいつの――!)
彼女は“天敵”に目を向けた。この場でこれほどの神秘を織りなす存在といえば、あの宝石の翁の関係者しかいない。
絶対無比とされた《朱き月》すら消し去った
並行世界を行き来する旅行者。
あの男ならば、この手の神秘を織りなすことができる。
(――いた!)
彼女は《世界》から情報を吸い上げ、あの男の関係者を探り当てた。
より広い《世界》を眺めれば、彼女が宝石の翁の弟子であることを理解したかもしれない。さらに目を広げれば、今だ魔法を自由に扱えない素人であることもわかったはずだ。だが、瞬時に読みとり、そう結論づけたアルクェイドが知り得た情報は、“天敵”のそばにいる黒髪の少女が、あの第二魔法に到達しているという事実だけだった。
知ろうとした情報のみ吸収する――それがアルクェイドの限界だ。
彼女だけではない。超越種の多くは、無意識的に知ろうと思った情報のみを《世界》から吸い上げてしまう。それは同時に、独断と偏見で既知と判断してしまった情報は吸い取らないことを意味した。
呼吸するように情報を吸い取るゆえの盲点。ゆえに超越種は、最高の賢者にして最悪の愚者でもある。これこそが《
ゆえに超越種は第二魔法が使えない。
第二魔法――並行世界の境界に干渉する力――は、だからこそ魔法なのだ。
アルクェイドは、その事実に気づいていない。
この違いを理解できる者は、第二魔法を操る“魔法使い”だけである……
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
――ガシャーン!
窓硝子が砕ける音と共に士郎の中で何かのスイッチが入った。
五軸の記憶に苦しんでいた彼の意識は、その一瞬で戦士のそれへと切り替わったのだ。
(なにが――!?)
割れたのはファーストフード店の二階の硝子窓。あの“絶対に相性が合いそうにない天敵”が見えていた窓が内側から外に向かって砕けていた。
しかも、そこから一直線に何かが飛び込んできている。
白い弾丸。
その行く手に、片膝をついて顔をしかめている凛の姿が――
「――
士郎は立ち上がり、駆け出しながら、自らの魔術回路を起動させた。
無数の剣が左腕の中から外に突き出ていく激痛が生まれた。
大した痛さではない。
霊的な回路、神秘を顕現させる媒体、魔力を巡らせる魔術回路の起動と稼働は、それ自体が肉体という監獄に捉えられた《人》の有り様に矛盾する現象だ。
作用には反作用が伴う。
激痛は、神秘を為すことへの反作用だ。
(間に合え――!)
士郎は記憶の中の“赤い騎士”を追いかけた。
それは別の世界線の記憶。
“赤い騎士”が自分であり、理想であり、絶望であることを知り、それでも彼に打ち勝ったという別の可能性が織りなした記憶。
その動きは持たざる者が修練の果てにたどり着いたもの。
その技はひとつしか持たないがゆえに身につけていった極みのひとつ。
ならば自分にできないはずがない。
なぜなら――
―― I am the bone of my sword () ――
「うぉおおおおおおお!」
刹那の間で数メートルの距離を詰めた。
両手には肉厚の双剣――
眼前に迫る白い弾丸。
躰が動く。双剣はほぼ同時に、迫る白い弾丸を十字に切り裂いた。
いや、切り裂いていない。
双剣は確かに何かに当たったが、意外なほど軽かったそれは、クルリと宙を舞いながら二十メートルほど離れた場所に着地している。
女性だ。
黄金色のセミロング、大理石のような白い肌、薄地の白いトレーナーに、動きづらそうな深紫色のロングタイトスカート――だがそれ以上に士郎を恐怖させたのは、美しい顔に輝く血のように真っ赤な双眸だった。
(殺される――)
理屈など存在しない。士郎は直感的にそう感じていた。
アレは《英霊》すら越えた存在だ。
純粋な脅威。
死をもたらす存在。
決して刃を交えてはいけない究極の兵器。
たとえ自分が剣であろうと、傷つけることすら適わない最強最悪の“天敵”。
「シロウ、邪眼を解放しました。私を見ないようにしてください」
不意の声と共に彼の傍らにライダーが踏み出してきた。
両手に持つのは柄から鎖を垂れ下げた無銘の短剣。服装は普段着通りだが、魔眼殺しの眼鏡を外し、その額に赤い呪印が浮かび上がらせている。
視線をあわさずとも睨みつけた対象を石化させるという宝石の魔眼。
仮に魔術耐性が強くとも、その身には重度のプレッシャーが掛かることになる。おまけに今のライダーは空前絶後の魔力火山、《根源の渦》と結びつく桜の使い魔である。それこそ今なら、魔王すら縛するアバドンの鎖に等しい拘束概念とさえ言える。
(……なんだ)
今更ながら、なぜ自分が、絶対的な脅威を切り弾けたのか、士郎は理解した。
この一年、リハビリもかねていろいろとやってきたが、だからといって衛宮士郎は衛宮士郎のままだ。あの“赤い騎士”にはたどり着けていない。だが、そう自覚できたことで、士郎の躰から余計な力が抜けていった。
自分はひとりではない。
それどころか、頼れる味方がふたりもいる。
「遠坂! アレはなんなんだ!?」
彼は白い脅威を見据えたまま背後の凛に尋ねた。
「《真祖》よ。吸血鬼の貴族。十字架もニンニクも利かないけど」
「姉さん!?」という桜の声。
「どうした!?」士郎が尋ねた。
「ごめん、向こうの邪眼にやられたみたい」
凛は平静そのものの口調で答えた。
「躰が動かないの。解除するまで時間を稼いで。そのあとは撤退」
「了解――桜、遠坂を頼むぞ」
「士郎さん……」
「大丈夫。あの時に比べれば……」
体調は万全。隣には頼れる《英霊》までいる。しかも相手は、いかに強くともたったのひとりだ。押し寄せるプレッシャーも、あの時に感じた“全人類の悪意と絶望”に比べれば、純粋すぎて逆に清々しい。おまけに時間さえ稼げば、凛という稀代の大魔術師が援護に入る。さらに今回は倒す必要すらない。
自分の魔術回路に不安が残るものの、それは“あれ”を使うことを前提にした時の話だ。
つまり、負ける要素がひとつも見あたらない。
「――そうだ」
士郎はふと思い出したことを凛に告げた。
「遠坂、まだ言ってなかったよな? “あれ”、使えるようになったんだ」
息を飲む気配が感じられた。
「だから大丈夫。時間稼ぎなら余裕さ」
「シロウ」とライダー。
「わかってる」
士郎は一対の双剣を握りながら自然体で身構えた。傍目にはだらりと両手を垂らしているだけに見えるが、これこそが、どのような攻撃にも対応できる鉄壁の構えだった。そうであることを教えてくれたのは、剣墓の荒野に立つ、遠い未来の“正義の味方”なのだが。
(さぁ、第一ラウンドだ)
士郎を気合いを入れ直した。
これは白い脅威との戦いではない。“赤い騎士”と自分との戦いだった。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.