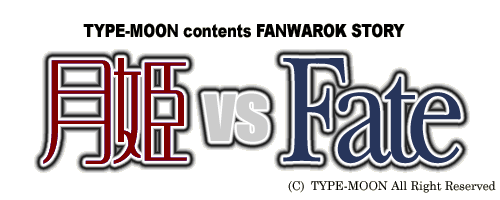
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[03]
-
3
「なんだ、ライダーも気づいてたんだ」
駅前ビルから出てきた
先の聖杯戦争で召喚された英霊の一騎。
振り当てられし
その正体は、遙か古代の東地中海で
もっとも、今の姿を見て正体に気づく者はいないだろう。
スレンダーながら魅惑的な曲線美を誇る肢体。
一級の細工物のように背に流れる紫色の長髪。
眼鏡の奥には、
(う~ん、さすがはアテナが嫉妬するだけの美人よね……)
「……リン、あそこにいるのは?」
「そうね……」
凛は一端両目を閉ざすと、片目だけ開き、ライダーが眺めているものを“視”た。
「真祖と《教会》の代行者。超越種と人間の混血がひとり。異能者が三人……
そう告げる彼女の瞳は青く変色していた。
「さすがです」
ライダーは穏やかな笑みを凛に投げかけていた。同性であっても、つい意識してしまうほどの笑顔だ。
「話に聞いていましたが、これほどのものとは」
「当然よ。こればっかりやってたようなものだし」
凛は照れくささを隠すようにムスッとしながら腰まで伸びた黒髪をかきあげた。
遠坂凛――桜の実姉にして、二十歳という若さで巨大な魔術刻印を編み上げた稀代の大魔術師。それが彼女の正体だ。
一部では“魔法使い”に最も近い魔術師とも囁かれている。
魔術と魔法は別物。魔術師は世界中に星の数ほどいるが、現存する“魔法使い”は世界でわずか数名しかいない。しかも、どのような魔法が存在するのか、全て知り得ている者すらほとんどいないという神秘の中の神秘である。
だが凛は、第二魔法と第三魔法の正体を知っていた。
それどころか、すでに媒体さえあれば第二魔法を行使できる段階にまでたどり着いている。
――これを自在に操るには、まず向こう側がどういう〝もの〟なのか瞬時に把握できなければならん。なに、その真似事なら、もうおまえもやってみせただろ。マナの有無を認識して、有る場所への穴を開ける――そのレベルを高めてやれば、これはもう、おまえのものだ。
最初の講義の時、師となった流浪の魔法使いは、笑いながら
その時には驚き、うろたえ、恥ずかしながらお手玉をしてしまった。
だがすぐに、彼女は自分が遠坂家の宿願にたどり着いていたことを理解した。
魔術は修練や鍛錬で身につけることができる。
魔法は違う。天性の素養、突然変異的な異能力、《人類》という種が、恒常的な魔術回路を捨て去ることで獲得した突破力――その果てに得られる“天性”の中でも、魔法に適した素養を持ち合わせていなければならない。つまり遠坂凛は、生まれながらにして第二魔法を会得した“魔法使い”であり、そうなることを運命づけられた存在なのだ。そうであると彼女が悟ったのは、つい最近になってからのことなのだが。
もっとも――
「まぁ……あの爺さん、やっぱりというか、放任主義もいいところでさ。こっち関係の修行っていったら、これしか教えてくれなかったのよ」
“これ”とは《世界》から情報を引き出す業――見るだけで物事の本質を理解する《
「それでも一年でそこまで鍛えるとは、さすがサクラの姉君です」
ライダーは素直に凛の力を賞賛した。
「誉めたってなにも――あっ、ライダーって桜のこと、マスターって呼ばないの?」
「頼まれましたから」
「あぁ、それで」
凛は顎で二人のもとに行くよう、ライダーに促した。
頷いたライダーと共に凛は歩き出す。
「でもまぁ、あの連中、無視していいんじゃない? そりゃあ、真祖と代行者が一緒にいるの、普通じゃ考えられないけど、それを言い出したらこっちだって普通じゃ考えられない組み合わせなんだし」
普通の魔術師では考えられないような反応だ。
半ば伝説の域にある吸血種の王族――真祖。
《教会》の暗部に君臨する十数名といない神の摂理を守護する者――代行者。
いずれも出会うだけで取り乱しかねないほどの大物だ。だが、大物という意味ではこちらも負けていない。なにしろ片や生ける《英霊》、片や“魔法使い”の直弟子。そのうえ、稟に至っては、二年前の聖杯戦争で“
(我ながら大物になったというか……)
麻痺しているだけという話もあるが、もはや多少のことでは動揺すらするまい――と、思っていたのだが。
「それについてですが」
ライダーは声を潜めた。
「サクラの中に英霊がいます」
凛は立ち止まった。ライダーも立ち止まる。
「……ゴメン、よく聞こえなかったんだけど、なんて言った?」
「《
「中って……まさか《聖杯》の中ってこと?」
「詳しいことは私にもわかりません。しかし、もともと《聖杯》は英霊の魂を満たす器だったはず。《
その言葉に、凛は眉を寄せ、考え込んでしまった。
「そっか……そういう可能性もあったんだ…………」
今の桜は全ての“力”の源泉、多くの魔術師が血眼になって追い求める《根源の渦》とつながるパイプそのものだ。そうでもなければ、存在を維持するだけで莫大な魔力を消費する英霊を使い魔にすることなどできない。
「とりあえず《
英霊は宝具と呼ばれる切り札を持っている。神話や伝説で語り継がれる現象や概念をそのまま再現してしまう“
そんなライダーが持つ宝具の中には“自らの力を封じる”という普通では考えられない特殊な宝具がある。
その名も《
なお、今の彼女は凛が仕入れた“魔眼殺しの眼鏡”を掛けている。そのためボンテージファッション風の目隠しにしか見えない《
「魔術は専門外ですが――私のわかる範囲では、機能していると思います」
ライダーは遠方を見やりながら、そう答えた。
釣られて視線を向けると、こちらに向かって歩いてくる士郎と桜の姿が見えた。
(どれどれ……)
帰省した直後にも確認したが、念のため、凛は目を細め、《
桜の全身、両腕はもとより、下は太股、一部は首筋から左頬にかけて、鮮やかな桜色に輝く蔓のような魔術刻印が存在している。それは全て、下腹部で脈動する純白の輝き、彼女の子宮に形成された《聖杯》を封じ込め、制御することに特化した特殊な魔術刻印だった。
(うん、まずまずのできじゃない)
魔術刻印を編んだ張本人は満足そうに頷いた。《
「遅いぞ、二人とも」
近づくなり士郎が不平を口にしてきた。
釣られて凛は《
「わっ!」
驚きの声をあげる。士郎と桜は、そんな凛を不思議そうに見やった。
(ま、まったく……自覚無しっていうか、なんて言うか…………)
凛も桜もライダーも反則的な存在だが、それに輪をかけて士郎のありかたは奇抜すぎる。
なにしろ――
―― I am the bone of my sword () ――
衛宮士郎という存在は、その言葉に集約されていた。
彼は剣であり鞘だ。
その身には史上最強の“鞘”が宿っている。
その心には史上空前の“剣”が収められている。
衛宮士郎は世界最強の剣――だからこそ彼は後に英霊となることが定められた人間だった。もっとも、その事実を知るのは、あのペンダントが語る真実に気づいた自分しかいないはずだが。
(だからこそ――)
一日も早く“魔法使い”にならなければならない。
《杯》と《剣》と《杖》と《盤》――そのうち《杯》が目の前にあり、《剣》もいずれ、《剣》に成る。ならば自分が《杖》にならなければならない。そして……
「遠坂?」「姉さん?」
不思議そうに士郎と桜が顔を覗き込んできた。
「うわっ!」
二度目の驚き。似たもの夫婦というか、どうもこの一年でこの二人は立ち振る舞いが妙に似てきたように思える。こうしてキョトンと見返してくる顔立ちなんかは呆れるほど瓜二つだ。
桜の実姉である凛がそう思うのだから間違いない。
だが、これはこれで別の意味で困ってしまう。なにしろ自分の心も、どうやらそういうことになりかけているとしか思えないわけなのだし。
「と、とにかく」
凛は照れ隠しに咳払いをした。
「ちょっと面倒そうな連中が近くにいるの! 買い物も終わったし、さっさと帰るわよ。いいわね!」
彼女はスタスタと歩き始めた。
「えっ? でも、このあとは公園で――」
士郎は手にしていたバスケットを掲げ上げた。
中には士郎が造った弁当が入っている。未来の英霊はこう見えて家事全般、なんでもこなす家庭的な少年なのだ。
「だから公園に行くって言ってるじゃない!」
「いや、帰るって……」
隣で桜もコクコクと頷いている。
「いいから!」
凛はくわっと八重歯を剥き出して怒鳴り上げた。
再びキョトンとする士郎と桜。だが、すぐに二人の頬はとろけるように緩んだ。
「そうそう、遠坂はこうだよな」
「はい、やっぱり姉さんはこうじゃないと」
「あんたたち、なにが“こう”なのか、じっくりねっとりたっぷりどっぷりほじくり返して――」
異変が起きたのは、まさのその時だった。
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.