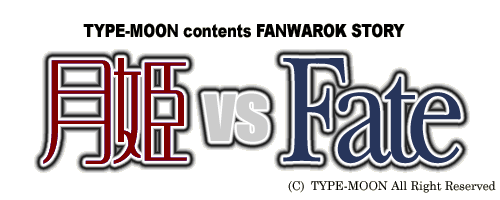
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[05]
-
5
アルクェイドは純粋に驚いていた。
超高速で駆け抜ける英霊に手こずるのは当然の結果だ。実を言えば、英霊と戦うのはこれが初めてではない。まだ真祖狩りの兵器にすぎなかった頃、なりゆきとはいえ、手強い英霊と戦った経験がある。今にして思うと、あれは《世界》と《人類》の双方にとっての危機だったのだろう。だからこそ二つの抑止力が出会ってしまい、不幸にも刃を交えることになった……
“世界の抑止力”たる真祖。
“霊長の抑止力”たる英霊。
両者は決して、相容れない存在だ。天敵と言っていい。
だからこそアルクェイドにはわかっていた。
紫髪の妖女は英霊だ。“石化の邪眼”でプレッシャーをかけ、自分に匹敵する人外の速さで一撃離脱を繰り返してくるところなど、並みの超越種など話にならないレベルにある。
それだけに彼女は驚いてもいた。英霊と共に戦う少年が、あろうことか――英霊と連携をとっているとはいえ――守りについては、自分と拮抗しているように感じられたからだ。
赤髪の少年。
両手に肉厚の双剣を持つ少年。
隙をついて宝石の翁の関係者に迫ろうとしても、どういうわけか鋼鉄の城壁のごとく全てを弾き続けている。
体調が万全に戻っている今、自分の両手は金剛石と並ぶ硬度を持っているはずだ。
下手な武具、並みの概念武装では防ぐことすらかなわない。
だが、少年は防いでいる。
何度目かの連撃で片方の剣を打ち砕いてみたが、次の瞬間には、剣が復活していた……
(――
それは究極の概念武装、《教会》の聖典と並ぶ霊長の切り札を意味する言葉である。
英霊がいるというなら、宝具があってもおかしくはない。だが、それを振るうのはごく普通の少年であるのだから妙な話だ。それなりの魔術回路を持っていることはわかるが、アルクェイドに言わせれば、彼程度の魔術回路は無いも同然の微弱なもの。シエルに比べれば、笑えるぐらいに大したことがない。その程度の魔術師が、宝具を操ることなど普通では考えられないことだ。
――ヒュッ!
再び真横から紫の閃光が駆け抜けた。
アルクェイドは後ろに飛び退く。
躰が重い。邪眼のせいだ。
これでは“切り札”を使えない。《世界》に干渉した瞬間、自分は無防備になってしまう。全力を出せば軽々と退けられるというのに、彼女の中の“アルク”が衝動を解き放つことを許さない。それでも衝動を抑える力を八割にし、残る二割を全て戦闘能力に費やしているというのに……
(なぜ――!?)
なにかがおかしい。
アルクェイド・ブリュンスタッドは真祖の姫。例え二割の力でも自分に敵う者など、そういるはずがない。
だが、苦戦している。
それも宝具を持つとはいえ、単なる魔術師の少年に。
(――何かが邪魔を?)
わからない。最強でこそあるが、全知全能ではないのだから。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
(士郎さん……)
片膝を付く姉の背後、その背中に手を押し当て、魔力を流し込んでいる桜は
二人の強さは知っていたつもりでいた。
だが、目の前で繰り広げられる戦いは彼女の想像を超えたものだった。
いや、もしかすると忘れていただけかもしれない。
聖杯戦争から二年――戦いの日々が遠い過去のものになりはじめている。だが、全てを忘れたわけではない。自分はあの時、罪もない人々を殺しているのだ。それも一人や二人ではない。幾人もの人間を捕らえ、喰らい、溶かし…………
忘れられるはずなどない。
今でも時折、死を持って償いたくなる。
だが、それは単なる逃げだと教えてくれた人がいた。助けられなかった人、踏みにじった命、切り捨てた未来、その全てに報いるためには“報いる”ために生きなければならない。そう教えてくれた人がいた。
だからこそ、交錯する世界線の中に今も間桐の家に囚われている自分を見出しても驚かなかった。
愛する人が姉と添い遂げ、この町を離れる世界線もあったが、寂しいとも悔しいとも思わなかった。
ひとつだけあるとすれば――愛する人が戻ってこなかった世界線。
(私が弱いから……)
それだけは絶対にあってはならない可能性だ。
強くならなければならない。
弱さに逃げてはダメだ。
ここで逃げては、あの時、自分が踏みにじった命はなんのために――
(……あっ)
桜は奇妙なものを目撃した。
白い怪物が飛びだしてきた場所、ファーストフード店の二階の窓から黒い少年が飛びだしてきたのだ。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「あのバカ!」
志貴は無茶を承知で壊れた窓の外に飛び出した。
二階から一階へと落下。
だがこの程度の活劇は馴れている。できれば転がることで衝撃を拡散したいところだが、地面には硝子の破片が飛び散っている状態だ。多少きつくとも両足で踏ん張るしかない。
「――くっ!」
着地。膝と腰に思い衝撃が走る。
「――そっ!」
志貴は顔をしかめながら駆けだした。同時にデニムパンツの後ろポケットから平らな棒状のものを取り出す。“
このナイフを自分に手渡すことも琥珀が奸計の一端だった――そういう世界線があったのだ。
いや、そんなことはどうでもいい。
片刃の刀身を飛び出させ、前のめりになりながら地を走り抜ける。
なにがなんだかわからない。
だが、異変が起き、アルクェイドが何かと戦うべく飛びだしていった。
つまり“敵”がいるということだ。
(――あいつ!?)
志貴はギョッとした。彼が向かう先、アルクェイドと激闘を繰り広げている相手は、敵意すら感じさせる眼差しを向けてきていた、あの赤毛の少年だったのだ。
(あいつか!)
理不尽な敵視とアルクェイドの振る舞い――その二つから、志貴は赤毛の少年を“敵”に分類した。
いや、それ以前に彼は赤毛の少年を敵と見ていた。
理屈など無い。
あれはイヤなやつだ。
断言できる。
あれは
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
「なっ――――――!?」
士郎は無意識的に、背後に飛び退いた。
直後、真横から迫った“死”の気配の白刃が空を薙いだ。
あの黒い少年――“天敵”だった。
「くっ――」
彼は地を削りながら勢いを殺すと、馴れた手つきで眼鏡を外し、黒シャツの胸ポケットに収めていた。
途端、士郎は殺気を越える死気とも言うべき濃密な脅威を全身に感じ取った。
(こいつ――!?)
危険だ。あまりにも危険すぎる。
先ほどから激突している白い脅威は、どちらかといえば、聖杯戦争中に対峙した《
いや、全ての理屈を超越した“死”そのものというべきかもしれない。
破滅でも消滅でも無い。それらを二次的なものとして従属させる、純然たる“死”の感覚そのもの……
当然の感覚だ。
衛宮士郎が“剣”の極みなら、遠野志貴は“死”の極みである。
もっとも、そのことを二人は知らない。
だが、幾たびもの死線をくぐりぬけた経験が、それぞれの本性を、お互い、直感的に感じ取らせていた。
「冗談だろ……」
士郎は自然体で身構えた。
直後――
「士郎さん!」
悲鳴に近い桜の声が響いた。
ハッとなり、振り返ろうとする。その隙をつくように黒い少年が地を蹴った。
(しまった――!?)
二重の意味で士郎は焦った。
視界の中、あの壊れた窓から飛びだしてくる新たな人影を見出したのだ。しかもそれは、どこからともなく両手に無数の剣を具現化させていた。
凛と桜のいる場所を睨みながら――
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
九軸の世界線の中に魅惑的なものがあった。だからだろう、シエルはその記憶に浸ってしまった。いや、できることなら、今からでもそうしてもらえれば個人的に嬉しいというか――
「あのバカ!」
その声でシエルは我を取り戻した。
「遠野くん!?」
顔をあげると志貴が窓から飛び降りるところだった。
アルクェイドの姿が無い。
それ以前に、濃密な霊圧を眼下の広場に感じ取る。
(あのバカ猫!)
両腕の“中”を確認する。収めた“黒鍵”は五十三ずつ。常日頃からこれほど持ち歩いている《代行者》は、《教会》広しといえどもシエルぐらいしかいない。なにしろシエルの異名の由来は――
(――とにかく)
まずは状況確認。秋葉はその場に座り込み、両手で頭を抱え、必至になって何かを抑えている。黒かった髪が真っ赤になっているところを見ると、鬼種としての衝動を抑えているところなのだろう。
「秋葉さま、大丈夫です。落ち着いて。落ち着いて……」
彼女の背中をさすっているのは、苦しげな表情の琥珀だ。
その後ろでは、グッと歯を食いしばっている翡翠が、どうにか手近なテーブルに手を付き、立ち上がろうとしていた。
他の人々は総じて気絶しているらしい。
都合がいい。
死んでいる者もいるかもしれないが、余計に騒いだり邪魔をしたりする者がいないということだけでも、何かと今後の処理が楽になる。
(外は――)
改めて外を見たシエルは――言葉を失った。
紫髪の美女が本気のアルクェイドと互角に戦っていた。そればかりか、隙を突いたアルクェイドが、見知らぬ二人の少女のもとに向かおうとすると、両手に肉厚の双剣を手にした少年が、人とは思えぬ恐るべき剣技で完璧にブロックしていた。
――でもすごいじゃない、ここの聖杯戦争。儀式のあとも英霊を残せるなんて、そうそうできるもんじゃないし。
アルクェイドはそう告げていた。
だとすると、あの二人は英霊なのだろうか。超越種であるアルクェイドなら一見するだけで判別が付くだろうが、シエルにはそこまでの力が無い。半ば超越種に近いとはいえ、シエルは単なる人間だ。
(とにかく――!)
状況は理解した。
英霊がいる。正体不明の異変が起きた。アルクェイドが本気になった。それを邪魔する女性と少年がいる。アルクェイドが狙うのは二人の少女。飛び降りた志貴は、そのままナイフを取り出し、赤毛の少年のもとに向かっている。
(――私が狙うべきなのは!)
シエルもまた、窓から外へと飛び出した。
同時に四本ずつ、計八本の“黒鍵”を具現化する。
一瞬の思考で魔術回路が起動。刹那の間に刀身が生まれた。
概念武装“黒鍵”――それは剣の形をした破壊の魔術だ。物理的な性能はお世辞にも良いとは言えない。名のある業物と斬り合えば、それだけで砕けるほど脆弱な武器だ。しかし、その刀身に秘められた破魔の力は並みのものではない。護符として見た時の“黒鍵”は十字架を溶かした銀の弾丸と同じ威力を持つ。
シエルは狙いを定めた。
二人の少女。
良く似た二人。
姉妹かもしれない。
黒髪と紺髪。危険なのは――紺髪の少女。
「破っ!」
シエルは両腕を交差するようにして八本の黒鍵を放った。
―― I am the bone of my sword () ――
(――!?)
信じられない出来事が起きた。横合いから別の“黒鍵”八本が飛来したのだ。
シエルの“黒鍵”が全て打ち砕かれる。
(まさか――!?)
“黒鍵”を持つのは《代行者》だけだ。だが、地面へと落下する中、シエルが目を向けた先にいるのは、あの赤毛の少年である。
彼の両手には、新たな“黒鍵”が握られていた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
(こいつ――)
眼鏡を外した瞬間、志貴は赤毛の少年が予想通りの“天敵”であることを確信した。
世界中が黒い線で埋め尽くされている。
煉瓦敷きの地面、真新しい街灯、ペンキが塗られたベンチ、新築の高層建築物――その全ての黒い線が走っている。ナイフをその線に走らせるだけで、どんなものでも切れてしまうという“壊れやすい部位”だ。
同様に赤毛の少年の躰にも無数の線が走っている。
特別に何かあるわけではない。
場所はちょうど喉の真下だが、極死の点も存在している。
つまり赤毛の少年は、ごく普通の人間だということになる。何か特別な超越種でもない。そのくせ、あのアルクェイドと瞬間的とはいえ、互角の勝負をしていた。
人であって人ではない――自分と同じだ。
ゆえに“天敵”。いずれ自分を踏みにじるであろう“正義の味方”。
「士郎さん!」
見知らぬ少女の声。ハッとなった赤毛の少年が振り返ってしまう。
致命的な隙。
志貴の躰は、考えるより先に動き出した。
(えっ――?)
駆け出しながらも、志貴はそんな自分に驚いていた。
(――殺す?)
このままいけば、自分は赤毛の少年を殺してしまう。
アルクェイドの敵を。自分の天敵を。“正義の味方”を。
「
赤毛の少年は振り返りつつ呪文のような言葉をつぶやいていた。
直後、彼は両手の双剣を手放し、何もないところから志貴が見知った武器を具現化させた。
(なっ――!?)
“黒鍵”だ。
シエルが手にするそれを、志貴は何度となく見ていた。だからこそわかる。
しかし、それは余計、彼を混乱させた。
詳しいことは聞いていないが、“黒鍵”は《教会》の人間だけが持ち得る護符だとシエルが話してくれたことがあったのだ。だとすると、この赤毛は《教会》の人間ということになる。
(まさか《埋葬機関》の……)
だとするとアルクェイドが本能的に挑み掛かった理由もわかる。今でこそ本気でぶつかることはないが、アルクェイドとシエルがことあるごとに反目している理由も、ある意味において、そのあたりに原因があるのだから。
(だったら――)
と志貴が思考を走らせようとした瞬間。
「破っ!」
シエルの声が聞こえた。
刹那、赤毛の少年は無言のまま、“黒影”を志貴から見て見当違いな方向に投げつけた。
そのフォームはシエルと瓜二つだった。
――ギンッ!
視界の隅で、赤毛の“黒鍵”が、シエルの“黒鍵”を迎撃していた。
志貴は急制動をかけた。
赤毛はさらなる“黒鍵”を両手に具現させている。その目は、地面に向け落ちようとしているシエルに――
(先輩が殺られる!?)
志貴は急制動をキャンセル、倒れ込むように、赤毛に迫った。
赤毛は背を逸らすように両腕をあげ、さらなる“黒鍵”を打ち込もうとしていた。
その背を、志貴は見た。
黒い線が走っている。
(――どうとでもなれ!)
背骨に走る太い黒線に、志貴は“
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
(――もう! なにやってんのよ!)
凛は士郎の危機を座して見るしかない自分に激怒していた。
あの白い脅威の邪眼は洒落になっていない。躰を縛られたのではなく、存在を縛ってきた。おかげで立ち上がることさえできない。それほどの呪詛を、凝視という一工程で行使するとは――考えるだけで凛は寒気を感じた。
しかし、今は恐れている時ではない。
一秒でも、一瞬でも早く、この呪詛を解呪しなければ――
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
(先輩が――!?)
桜もまた、同じものを見ていた。
自分たちを守るための一撃。それゆえに生まれた絶対の隙。“死”を体現する黒い少年がその背に迫り、今まさに白刃を縦一線に、下段から上段へと振り上げようとしている。
間に合わない。
叫んでも間に合わない。
ライダーは白い脅威とぶつかっている。間に合わない。
“影”を伸ばしても間に合わない。
姉も間に合わない。
彼を救うことができない。
守るべき者がいない。衛宮士郎を守るべき者が。“鞘”を守る“剣”が――
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
白光の爆発が起きた。同時に志貴は、右腕に強い衝撃を覚えた。
ナイフが弾かれた。
そうと理解した瞬間、志貴は蒼白の脅威を察知していた。
「なっ――!?」
考えるより先に躰が動く。
凝視。線の認識。行動――が間に合わない。
「くっ――」
上段から振り下ろされるそれを、志貴は左に飛び退くことで避けた。
脅威は消えない。
蒼白の鉄槌。ナイフでかなう相手ではない。
「志貴ぃぃぃ!」
アルクェイドの声。白い脅威が蒼白の鉄槌とぶつかる。
「遠野くん!」
グッと襟首が引っ張られた。次の瞬間には宙を跳んでいる。
「うわっ!?」
それでもどうにか地面に転がる。
「なにが――!?」
もう頭の中は考えるべき事柄でいっぱいだ。
ただ、蒼白の鉄槌の正体は理解できた。
青い騎士だ。
白銀と碧とで構成されたドレスのような鎧を身につけた騎士が、何かを突き出すような姿勢で、座り込んでいる赤毛の少年の傍ら立っていた。おそらく手にしているのは剣か何かだろう。だが、志貴の眼には、それが何であるか見えなかった。透明な武器らしい。よくよく目を凝らすと、騎士が持つ“何か”の“死の線”を見ることができた。大きさから見ると、刀剣の類に思えるのだが……
「遠野くん、大丈夫ですか?」
尻餅をついている志貴の傍らにシエルが着地した。
両手には“黒鍵”。瞳は鋭く、赤毛の少年と青い騎士を睨んでいる。
「冗談でしょ……」
志貴を挟んで反対側にアルクェイドもやってきた。その瞳は鋭さを称えたままだが、理性の輝きが垣間見えた。どうやら少しは落ち着いたらしい。困ったお姫様だ。これで少しは状況を聞けるかもしれない。
「アルク、なんなんだ、あいつら」
志貴は立ち上がりながら彼女に尋ねた。
「“魔法使い”とその一行よ」
「“魔法使い”!?」
驚きの声をあげているのはシエルだ。
「多分ね」
アルクェイドは髪をかきあげた。
「本人じゃないけど、奥でしゃがんでるのが宝石の翁の関係者。それだけは間違いないわ」
「待てよ。俺にもわかるように――」
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
背後で起きた突然の衝撃で士郎は無様にも転がっていた。そのまま起きあがろうと尻餅をついた姿勢で振り返った先に――彼女がいた。
「……えっ?」
碧と銀のドレスのような鎧。
手にするのは不可視の剣。
編み、結い、束ね上げられた黄金色の髪。
その躰は驚くほど小柄で、その腕は驚くほど細く、それでいながらその身にまとう空気は凛々しく、雄々しく、爽やかな風を思わせる……
「……シロウ」
懐かしい声で、懐かしい言葉が紡ぎ出された。
士郎は黙り込む。
告げるべき言葉が思いつかない。
それは彼女も同じだった。だが、彼女は剣を降ろすと、しばし自らの胸に手をあて、告げるべき言葉を見出した。
「――問おう。貴方が、私のマスターか」
彼女は振り返った。
思い出されるのは、まだ自らの運命を何も知らなかった頃の土蔵での出会いの瞬間。
だがここは土蔵ではない。
そして、振り返った彼女の顔に浮かぶのは――
「召喚に従い参上した。これより我が剣は貴方と共にあり、貴方の運命は私と共にある」
律儀にも手順を繰り返す少女。
その瞳は、懐かしさと照れくささと喜びがない交ぜに――
死にたくない!
役者は揃い、因果が崩れた。
そして偶然と必然と奇蹟と運命によって、第十と第六の世界線が紡ぎ出された。
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.