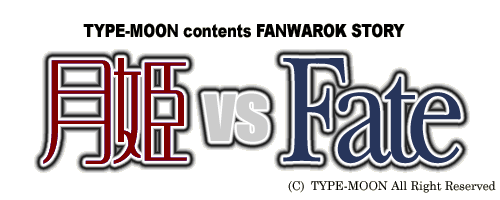
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[02]
-
2
(……気のせいか?)
ファーストフード店の二階、窓辺の席に腰掛けた
見られている気がした。
いや、間違いなく、赤毛の少年はこちらを凝視していた。
距離は約二百メートル。顔立ちが判別できるような距離ではない。少なくとも自分はそうだ。しかし、寸前まで感じ取れてた眼差しには敵意のようなものすら感じられた。
実はこちらが見えないだけで、向こうには見えていたのでは?
ありえない話ではない。
志貴の眼は特別仕様だが、だからといって視力が良いわけではない。そして、あの赤毛の少年が鷹の目の
「んっ? どうかした?」
「いや、ちょっと」
志貴は頬杖をやめ、テーブルを挟んで反対側に座る女性に視線を戻した。
と、彼はゲンナリとした表情になった。
「おい……」
「むぁみぃ?」
対面の女性はハンバーガーを口に詰めたまま尋ね返してきた。
どうやら自覚していないらしい。困ったものだ。
今や店中の視線が彼女に集まっている。当然だろう。彼女の前にはハンバーガーの包みが山のように積み上げられている。そのうえ、彼女自身、黙っていても衆目を集める容姿の持ち主なのだ。
抜群のプロポーション。肩口まで伸びる黄金色の髪。抜けるような白い肌。
だが、彼女の正体を知れば、誰もが我先とばかりに逃げ出すはずだ。
それもまた然り。
なにしろ彼女は“人ならざる者”なのだ。
一般に吸血鬼と呼ばれる超越種にして、その中でもさらなる高みに君臨する《真祖》の姫君。
その概念に《朱い月》の可能性を秘める存在。
ただ一度の過ちから、他の《真祖》を滅ぼしてしまった罪深き《白き姫》。
アルクェイド・ブリュンスタッド――それがどれほど規格外で狂気ぢみた存在であるか、正確に把握できる“モノ”などこの世には存在しない。なぜなら彼女を正確に把握しうる“モノ”は、すでに“この世”から外れた化け物以外の何モノでもないのだから。
しかし。
「(ゴクンッ)――で、なに?」
「“なに?”じゃないだろ」
志貴は仕方なく備え付けの紙ナプキンを取り、彼女の口元にベッタリとついたソースやら何やらを拭いていった。その間、彼女は大人しく拭かれるがままになっている。まるで幼子だ。いや、拭かれている間、目を細めているところを見ると猫と言うべきかもしれない。
「食べるなとは言わないから、もう少し行儀良くしたらどうだ?」
「いいの、いいの。そういう場面じゃないし」
ニパッと笑ったアルクェイドは新しいハンバーガーを掴むと楽しげに包装を解き、両手で持ったそれを美味しそうに食べ始めた。
そんな姿に、志貴の目元は自然と和らいでいった。
(うまそうに食べるよな……)
彼女と出会ってすでに二年。長かったようにも思えるが、振り返れば刹那の時間だったとしか思えない。
そもそも遠野志貴という人間は、穏やかで怠惰な生活を理想とする典型的なダメ人間だ。理想を言えば、今も彼の太股の上で丸まりながら眠り続けている黒い仔猫――首輪の代わりにリボンを付けている仔猫――のように、ポカポカした日向でノンビリと昼寝ばかりしていられれば最高だとさえ思っている。
だが、どうにも環境が怠惰であることを許してくれない。
家にいれば家にいたで妹が口うるさい――嬉しいことだが。
使用人の一方はそんな彼を笑い、もう一方はジッと見据えてから溜息をつく――これもまた嬉しいことだが。
大学でもうるさい悪友が何かと引っ張り回し、カレー好きの先輩は何かといえばアルクェイドと火花を散らしている――これらについて微妙にどうにかして欲しい。
つまるところ。
そういう環境にあるからこそ、志貴という人間は安心して怠惰なダメ人間になることができていた。特に目の前にいる猫のような白いお姫様がいてくれなくては、“生きる”という無駄と無意味の極地を楽しむことすら難しかったかもしれない。それを思えば、こうして無理矢理旅行に連れ出されたのも、それほど悪い気は……
(あっ!)
ようやく志貴は本題を思い出した。
「なぁ、アルク。せめて家に電話するぐらい――」
「むぁめぇ」
ダメ――と言っているらしい。
「いや、でも、さすがにマズイだろ。アルクと旅行するのはかまわないけど、とりあえず生きてることぐらい連絡しないと、逆にマズイことになると思わないか?」
「(ゴクンッ)――逆にって?」
九個目のハンバーガーを手にしながらアルクェイドが尋ね返した。
「考えてみろ。今頃、秋葉はもとより先輩とかも、俺のこと探してるぞ。絶対に」
「あぁ、無理無理。シエル、もうロアじゃないから私の居場所とかつかめないし。それに妹だっていろいろと忙しいんでしょ? 学校とか学校とか学校とかで」
「……甘いぞ、それ」
志貴は重々しい溜息をついた。
「それで済むなら普段から俺は――」
「兄さん!」「遠野くん!」
二つの声が店の窓硝子をビリビリと震え上がらせた。
「――やっぱり」
志貴は深々と溜息をついてからクルリと体の向きを階段のある方向へと向けた。
そこには二人の女性の姿があった。
志貴から見て左側にいるのは、腰まで届く長い黒髪が印象的な細身の少女だ。襟首に赤いリボンをつけた白いブラウスと抑えられた朱色に染まるロングフレアスカート、左腕に薄茶色の春物ジャケットをひっかけているところを見ると手荷物らしい手荷物は右手に持つ小さなハンドバックひとつらしい。
一方、右側にいる女性――群青色のショートヘアと伊達眼鏡がよく似合う女性――は、巨大な旅行用トランクを左肩に担ぎ上げていた。服は空色のジャケットとパンツ、白いブラウスというフォーマル寄りの服装というもの。それだけに、トランクを担ぎ、全身でハァハァと息をしている姿はシュールでさえある。
いずれにせよ。
「……やぁ」
「「“やぁ”じゃありません!」」
二人はズカズカとテーブルに歩み寄り――伊達眼鏡の女性がダンッとトランクを床に置いた。
直後。
「兄さん! 遠野家の長男というお立場を考えてくださいと何度も何度も何度も何度も言ったはずですが、お忘れになられましたか!?」
黒髪の少女はダン!――とテーブルに両手を叩きつけた。
戸籍上は志貴の実の妹、しかし実際には血のつながらない義理の兄妹という複雑な間柄にある志貴の“家族”だ。
「いいえ、秋葉さん。遠野くんは誘拐されただけです。悪いのは、真夜中に窓から侵入したと考えられる、どこぞの非常識な吸血鬼です」
伊達眼鏡の女性はキッとアルクェイドを睨みつけた。
シエル。
志貴と同じ大学に通う一個上の先輩だ。もっとも、志貴が高校二年生の時には同校の三年、三年になった時には同校の教師、彼が大学に進学すると同じ文学部の一年先輩という社会的立場にあり、今現在は「志貴が高校一年生の頃からの先輩後輩という間柄」という社会情報を“作り上げてきた”だけという間柄にすぎない。だが、これについて志貴も他の面々も、特にこれといって追求したことは一度も無い。
いや、教師になった時にはそれなりにあったといえばあった。同じ方法でアルクェイドが英語教師になり、面白いからというただそれだけで、今も秋葉の後ろに控えている二人の使用人を編入生に――
「こ、
「あははは、とりあえずご無事のようですね」
「………………」
そこには遠野家に仕える一卵性双生児の使用人――
エプロンと髪飾りこそ外しているが、黒い古風なワンピース状のドレスを身につけ、ピシッと背筋を伸ばして無言のまま軽く頭を下げてきたのが翡翠。
まるっきり対照的な双子だ。
しかし、いくらなんでも二人とも秋葉に付いてくるとは――
(……いや、ちょうどいい機会だし)
これまでいろいろとあったが、このメンバーで旅行をしたことなど一度も無かった。
“あの騒動”から二年も過ぎている。
怠惰なダメ男は“家族”を手に入れ、こうして騒がしい毎日を楽しめるまでになっていたる。その喜びを今は素直に――
「あっ――ところでさ、シエル」
言い争いを続けていたアルクェイドが何気なくシエルに尋ねた。
「ここって、もしかして例の聖杯戦争の舞台?」
「わかっているなら――!」
「へぇ、やっぱり……」
彼女は鋭い眼差しを窓の外に向けた。
一瞬にしてシエルの表情が強ばる。隣にいる秋葉も同様だ。平然としているのは、この手の急激な変化に免疫ができてしまった遠野志貴ただ一人だけだ。
「何が“やっぱり”なんだ?」
志貴は冷め切ったホットコーヒーで口を湿らせながらアルクェイドに尋ねた。
「“天敵”がいるの」
彼女は答えた。志貴の鼓動が一拍だけ止まる。
「前に教えたよね。私が《世界》の抑止力……《人》の天敵だってこと」
チラリと差し向けてきたアルクェイドの瞳は血のように真っ赤だ。
馴れたといえは、やはり背筋がゾクリとする。
内なる声が警鐘をならした。
――殺せ
それは血脈に宿る意志。《人》を守ることだけに特化した概念がもたらす意志。その声に従った瞬間、彼は遠野志貴ではなく
「……それで?」
彼は衝動を抑えきってからアルクェイドに尋ね返した。
「だから、いるのよ。《人》の天敵の天敵が」
アルクェイドは再び窓の外を見つめた。
志貴、シエル、秋葉がその眼差しを追いかける。
百メートルほど先、春光に照らし出された駅前の広場の一角に、紫色の長髪をなびかせるスレンダーな女性の姿があった。
黒いパンツに黒いトレーナー、膝まで達する長い髪は腰のあたりで深紫色のリボンを用い束ねているらしい。一瞬だけ陽光を照り返したところを見ると、顔には眼鏡をかけているようだ。
「アルクェイド、あれがなにか、わかるんですね?」
ただ者ではないと感じたのだろう、真剣な表情のまま、シエルはアルクェイドに尋ねた。
「まぁね」
アルクェイドは肩をすくめ、新たなハンバーガーの包装を剥がしにかかった。
「でもすごいじゃない、ここの聖杯戦争。儀式のあとも《英霊》を残せるなんて、そうそうできるもんじゃないし」
シエルが絶句していた。
志貴が不思議そうに眉を寄せる。
「なんだ、その《英霊》とか聖杯戦争って」
アルクは難しいことはパスとばかりにシエルを一瞥してからハンガーバーにパクついた。
「……難しいことは省きます」
代わってシエルが志貴に答えた。
「《聖杯》はわかりますか? 磔にされたイエスの血を受けた杯のことですけど」
話がオカルトぢみてきた。志貴はアルクェイドを見やり、いつものようにしてくれと目で訴えかける。すると彼女は得意げにウィンクを投げ返してきた。
周囲を一瞥する。
あれほど集まっていた衆目がウソのように無くなっていた。退席させるほどの強制力を持たせていないらしい。だが、このテーブルの周囲に対する感心と興味と認識を阻害する力はあるようだ。“力”を持つ者に対しては無意味だが、これで安心して話を続けられる。
「あぁ、うん。知ってる。確かヒトラーが探し回ったとかいう」
「正確にはヒトラーの後ろにいたモノですが――」
シエルは言葉を切り、少し考え込んだ。
「――でも、遠からずです。《聖杯》は手にいれた者のどんな願いも叶えてくれます。少なくとも、ここで行われる聖杯戦争の《聖杯》はそう言われるものです」
「……それって、《聖杯》は何個も存在するってこと?」
「そうですね……《聖杯》という概念が存在すると考えてください。いわば《聖杯》を手に入れるという行為は、《聖杯》という概念を再現する魔術儀式そのものなんです」
「ええっと……」
「その大儀式を聖杯戦争と言います。儀式の参加条件は二つ。魔術師であることと、《聖杯》に選ばれた
「この町が?」
「ここは日本でも屈指の一等霊地なんです。確かアインツベルンが器を、遠坂が土地を、マキリが手順を作り上げたとか……最初の聖杯戦争は二百年以上前のことですし、その頃、《教会》の目を盗んで聖杯顕現の儀式をやるなんて、こんな極東でも無い限りできるはずありませんし」
「へぇ、それで日本なのに《聖杯》なんだ――あっ、それで《英霊》は?」
「《聖杯》が呼び出す
「なんか言った?」アルクェイドはジロリとシエルを見た。
「えぇ、いろいろと」シエルはニコリと微笑み返した。
一触即発。
だが、それもいつものことなので志貴は別段、気にしなかった。
「……んっ?」
と、彼はようやく、秋葉が無言のまま窓の外を見据えていることに気が付いた。
「秋葉、どうした?」
それでも彼女は黙り込んだまま窓の外を眺め続けている。
その姿は何かを思い出そうとしているようにも見えるが……
To Be Continued
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.