<<BACK [ CONTENTS ] NEXT>>
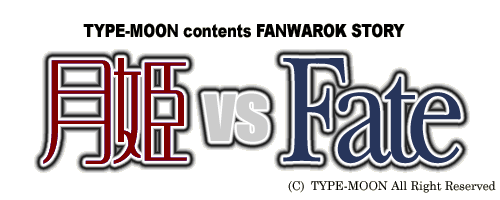
※本作は『 TYPE-MOON 』の作品をベースにした二次創作物です※
[00]
- prologue -
(――――――んっ?)
それは慣れ親しんだ“終末”と違っていた。
なにより苦痛が無い。 光が、音が、匂いが、味が、熱が、痛みが、苦しみが、叫びが、全てが抜け落ち、完全なる静寂に包まれ、静寂すら失われていく感覚――眠りに似ていながら魂が鈎爪で削られていく責め苦――が無いのである。
(――なぜだ?)
“彼”は考えた。
同時に“考える”という主体的な現象を起こしている自分に驚いた。
おかしい。
いや、違う。
これこそが本物なのだ。“あの力”がもたらした本物の……
(なるほど)
“彼”は苦笑した。
苦笑するべき顔という部位を持ち合わせていないが、それでも“彼”は苦笑していた。
本物の終わり。
そこには苦痛など、欠片も存在していない。
当然だ。
作用には反作用が伴う。何かを為すには、ただ為そうとするだけで代価が求められる。
つまりは、そういうことだ。
ただそれだけのことだったのだ。
――イヤだ!
誰かが叫んだ。
――イヤだ! イヤだ! イヤだ! 俺は! 俺はまだ!
それは“彼”の中にあるものだった。
(なるほど……)
立場が逆転している。だが、それもまた当然の結果にすぎない。
“終末”を迎えた時は彼が主であり“彼”は従だった。いや、その時の“彼”は己を意識することすらできない魔術回路そのもの。すでに従とすらいえない状態にあった。だからこそ、“あの力”で先に“終末”を迎えていたのは彼であり、“彼”ではなかった。
もちろん、その差は吐息ひとつ分しかない。
すでに“彼”は彼であり、“彼”という現象は知識を付随した魔術回路の一種にすぎず、こうして思考という現象を自覚できているのも、結局は彼という現象に内包された思考という現象への支配力が……
“彼”はギョッとした。
別の声だ。
一瞬にして無限の時間の中、“終末”へと向かう道程に異なる現象が存在していた。
――イヤだ! イヤだ! イヤだ! 俺は! 俺はまだ! 俺はまだ!
彼が叫ぶ。
別の声も叫ぶ。
――イヤだ! イヤだ! イヤだ! 俺は! 俺はまだ! 俺はまだ! 俺はまだ!
ふたつの声が重なった。
そして第三の声が響く。
――ううん…………は死なないよ。だって、この門を閉じるのはわたしだから。
彼方 にして此方 () から響く少女の声は、“終末に至る道程”という現象を大きく揺るがした。
――じゃあ奇蹟を見せてあげる。前に見せた魔術 () の応用だけど、今度のはすごいんだよ。なんていったって、みんなが見たがってた魔法なんだから。
(これは……)
“彼”は己という魔術回路から知識を組み上げた。
(……《聖杯》?)
“彼”に匹敵する妄執を糧に、“彼”とは異なる手段を選び、それでも“彼”と同じ結果を求め続けた狂える一族の祭具――だが、おかしい。それが使われるのは、もっと先のはずだ。少なくとも前回から十年程度しか経っていない。“あれ”を行うには六十年もの歳月をかけ、《大聖杯》に魔力を貯えなければならないはずだ。そうでもしなければ《大聖杯》は起動せず、穴も開けられず、英霊を七騎も呼び出せず、《聖杯》を満たすことも……
――じゃあね。
《聖杯》は微笑み、パタンと、《大聖杯》の門を閉ざした。
因果が、歪められた。
それは不完全だったゆえに、不完全な結果を導き出してしまった。だからこそ、《世界》は可能な範囲で、可能な現象を用い、可能な状態まで修整した。ゆえに《世界》は現象の中心に干渉した。
そこで不完全な第二魔法 () が使われていたことも承知の上で。
作用には反作用が伴う。
何かを為すには、ただ為そうとするだけで代価が求められる。
それだけのことだ。
ただ、それだけのことだった。
それは慣れ親しんだ“終末”と違っていた。
なにより苦痛が無い。 光が、音が、匂いが、味が、熱が、痛みが、苦しみが、叫びが、全てが抜け落ち、完全なる静寂に包まれ、静寂すら失われていく感覚――眠りに似ていながら魂が鈎爪で削られていく責め苦――が無いのである。
(――なぜだ?)
“彼”は考えた。
同時に“考える”という主体的な現象を起こしている自分に驚いた。
おかしい。
いや、違う。
これこそが本物なのだ。“あの力”がもたらした本物の……
(なるほど)
“彼”は苦笑した。
苦笑するべき顔という部位を持ち合わせていないが、それでも“彼”は苦笑していた。
本物の終わり。
そこには苦痛など、欠片も存在していない。
当然だ。
作用には反作用が伴う。何かを為すには、ただ為そうとするだけで代価が求められる。
つまりは、そういうことだ。
ただそれだけのことだったのだ。
――イヤだ!
誰かが叫んだ。
――イヤだ! イヤだ! イヤだ! 俺は! 俺はまだ!
それは“彼”の中にあるものだった。
(なるほど……)
立場が逆転している。だが、それもまた当然の結果にすぎない。
“終末”を迎えた時は彼が主であり“彼”は従だった。いや、その時の“彼”は己を意識することすらできない魔術回路そのもの。すでに従とすらいえない状態にあった。だからこそ、“あの力”で先に“終末”を迎えていたのは彼であり、“彼”ではなかった。
もちろん、その差は吐息ひとつ分しかない。
すでに“彼”は彼であり、“彼”という現象は知識を付随した魔術回路の一種にすぎず、こうして思考という現象を自覚できているのも、結局は彼という現象に内包された思考という現象への支配力が……
ウソだ!――
“彼”はギョッとした。
ウソだ! ウソだ! ウソだ! 僕は! 僕はまだ!――
別の声だ。
一瞬にして無限の時間の中、“終末”へと向かう道程に異なる現象が存在していた。
――イヤだ! イヤだ! イヤだ! 俺は! 俺はまだ! 俺はまだ!
彼が叫ぶ。
ウソだ! ウソだ! ウソだ! 僕は! 僕はまだ! 僕はまだ!――
別の声も叫ぶ。
――イヤだ! イヤだ! イヤだ! 俺は! 俺はまだ! 俺はまだ! 俺はまだ!
ウソだ! ウソだ! ウソだ! 僕は! 僕はまだ! 僕はまだ! 僕はまだ!――
ふたつの声が重なった。
死にたくない!
そして第三の声が響く。
――ううん…………は死なないよ。だって、この門を閉じるのはわたしだから。
――じゃあ奇蹟を見せてあげる。前に見せた
(これは……)
“彼”は己という魔術回路から知識を組み上げた。
(……《聖杯》?)
“彼”に匹敵する妄執を糧に、“彼”とは異なる手段を選び、それでも“彼”と同じ結果を求め続けた狂える一族の祭具――だが、おかしい。それが使われるのは、もっと先のはずだ。少なくとも前回から十年程度しか経っていない。“あれ”を行うには六十年もの歳月をかけ、《大聖杯》に魔力を貯えなければならないはずだ。そうでもしなければ《大聖杯》は起動せず、穴も開けられず、英霊を七騎も呼び出せず、《聖杯》を満たすことも……
――じゃあね。
《聖杯》は微笑み、パタンと、《大聖杯》の門を閉ざした。
因果が、歪められた。
━━━━━━━━◆━━━━━━━━
それは不完全だったゆえに、不完全な結果を導き出してしまった。だからこそ、《世界》は可能な範囲で、可能な現象を用い、可能な状態まで修整した。ゆえに《世界》は現象の中心に干渉した。
そこで不完全な
作用には反作用が伴う。
何かを為すには、ただ為そうとするだけで代価が求められる。
それだけのことだ。
ただ、それだけのことだった。
prologue - END
<<BACK [ CONTENTS ] NEXT>>
Copyright © TYPE-MOON / Bookshelf All Right Reserved.